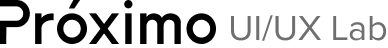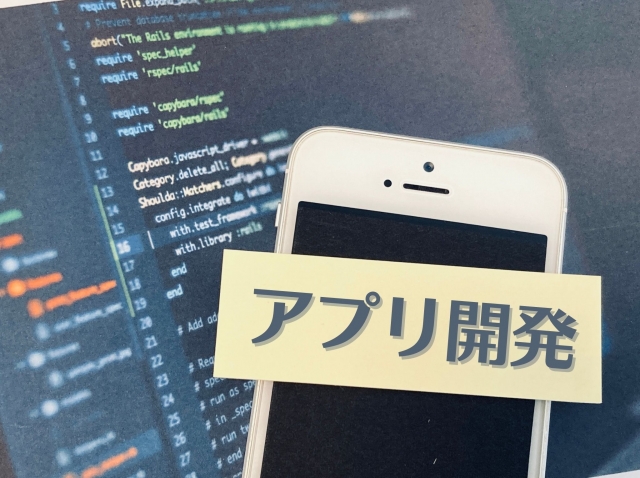UI/UX改善の重要性とは?成果につながる4つのポイント
UI/UX改善は、サイトやアプリの成果を大きく左右する重要な要素です。見た目のデザインだけでなく、ユーザーが「使いやすい」「快適だ」と感じる体験を提供できなければ、離脱率の増加やコンバージョン率の低下を招きかねません。競合に差をつけ、成果を高めるにはどのような改善が必要なのでしょうか。
今回は、成果につながるUI/UX改善のポイントについて解説します。
目次
UI/UX改善の重要性

自社サイトやアプリの成果を高めるためには、単なるデザインの刷新ではなく、ユーザー体験全体を見直す「UI/UX改善」が不可欠です。ここでは、その重要性を具体的な観点から解説します。
ユーザー体験の質を高められる
UI/UX改善は、ユーザー体験の質を底上げできます。現在は、顧客がサービスに触れる接点が多様化しており、Webサイト、スマートフォンアプリ、SNS、チャットツールなど複数のチャネルにまたがって体験するケースが一般的です。
そのため、各接点で統一された良質なUI/UXを提供することで、ユーザーは一貫した快適さを感じ、サービス全体に対する信頼や愛着が高まります。
ユーザー満足度を向上させる
UI/UX改善は、顧客の満足度向上にも直結します。ユーザーの視点に立ち、直感的に操作できるデザインや分かりやすい導線を整備することで、利用者は「快適に使えた」というポジティブな体験を得られます。
また、洗練されたUIはブランドへの信頼を強め、リピーター獲得やエンゲージメント強化に直結します。結果的に、ブランド価値向上にもつながるのです。
ユーザーの意思決定を促進する
優れたUI/UXは、ユーザーの意思決定をスムーズにします。操作が直感的であれば、利用者は迷うことなく目的の行動に移れます。
例えば、ECサイトで商品を購入する際、カートから決済までの流れがシンプルで分かりやすければ、購入完了率(コンバージョン率)は自然と上がります。
逆に、情報が分散していたりボタン配置が分かりにくかったりすると、ユーザーは途中で離脱してしまいます。
UI/UX改善は、このような離脱リスクを軽減し、意思決定を後押しする大きな役割を果たします。
UI/UX改善の具体的なプロセス

ここでは、リサーチから最終的なUI設計に至るまでの、UI/UX改善の具体的な流れを解説します。
UXリサーチによる現状把握
最初のステップは、現状を正しく把握することです。UXリサーチでは、定量調査と定性調査を組み合わせることで、数字だけでは見えないユーザーの行動や心理を明らかにします。
例えば、Googleアナリティクスやヒートマップで離脱率やクリック状況を数値で捉えつつ、インタビューやアンケートで「なぜそうしたのか」という理由を深掘りすることが有効です。
また、専門家によるヒューリスティック評価(デザイナーの視点でのチェック)を実施することで、一般的なユーザビリティ原則に照らした課題を洗い出せます。
さらに、ターゲットユーザーを実際に招いて行うユーザビリティテストでは、操作のしにくさや不明点が具体的に可視化されます。こうした多角的な調査を通じて、サービスの現状課題とあるべき姿を明確にできるのです。
仮説検証・改善
リサーチで得られたデータやインサイトをもとに、課題解決の仮説を立てる段階です。
ここでは「ボタンの配置を変えれば離脱が減るのではないか」「説明文を簡潔にすれば理解が深まるのではないか」といった具体的な改善案を出します。
仮説を立てたら小規模に検証を行い、結果をフィードバックして次の改善に反映しましょう。A/Bテストや限定的なUI改修を繰り返すことで、現状と理想とのギャップを徐々に埋めていくことが可能です。
プロトタイプの作成と最適化
次に、改善の方向性が固まったら、プロトタイプを作成します。これは完成品の前段階であり、UIやUXのアイデアを実際の操作に近い形で確認できるものです。
プロトタイプをユーザーに試してもらうことで、「使いやすさ」「分かりやすさ」が実際に担保されているかを早期に確認できます。この段階で得られるフィードバックは、開発コストが大きくなる前に軌道修正を行える点で非常に重要です。
さらに、複数のバージョンを作り比較検証することで、より効果的なUI/UXの最適化が可能になります。
最終的なUI設計
プロトタイプでの検証を経て、最終的なUI設計に移行します。ここでは、ブランドイメージを反映しつつ、一貫性のあるデザインを適用していきます。色、フォント、ボタンのスタイルなどのビジュアル要素を統一し、ユーザーに安心感を与えることが大切です。
さらに、エンジニアと密に連携することで、設計意図が正確に反映されたUIを実現できます。最終設計は「見た目の美しさ」だけでなく「使いやすさ」と「成果への貢献度」を兼ね備えた形に落とし込むことが求められます。
成果につながるUI/UX改善のポイント

UI/UX改善を成果につなげるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、UI/UX改善で意識すべき具体的な視点を解説します。
目的とゴールを明確に定める
UI/UX改善の目的とゴールを具体的に定めることが重要です。
改善を進める上で「離脱率を10%改善する」「ECサイトの購入完了率を20%向上させる」などの具体的な目標を設定することで、改善の方向性が明確になり、成果の測定もしやすくなります。
目的があいまいなままでは、デザイン変更や新機能追加といった施策が単発的に終わってしまいやすいのです。
具体的な数値目標やKPIを設定することで、改善効果を客観的に評価でき、関係部門を巻き込んで進めやすくなります。
ユーザーニーズを正確に把握する
UI/UX改善の出発点は、ユーザーを正しく理解することにあります。これによって、改善の優先順位を明確にでき、無駄のない施策につながります。
そのため、UXリサーチではアクセス解析やヒートマップといった定量データに加えて、インタビューやアンケートといった定性調査を組み合わせ、ユーザーがどこで迷い、どんな不満を抱えているのかを具体的に把握しましょう。
例えば、あるアプリの離脱率が高いとき、単に「UIが分かりにくい」のではなく「目的の情報にたどり着くまでにステップが多すぎる」といった根本的な課題が隠れていることもあります。
検証と改善を繰り返す
UI/UX改善は一度で完成するものではなく、仮説の検証と改善を繰り返すプロセスが欠かせません。
例えば、購入ボタンの位置を変える、説明文を簡潔にする、といった小さな仮説を立て、A/Bテストやプロトタイプで検証します。その結果をもとに改善を重ねることで、ユーザーにとって最適な体験に近づけていくのです。
この反復的なアプローチを取ることで、リスクを抑えつつ改善の効果を高められます。また、短いサイクルで改善を繰り返すことは、スピード感のある意思決定にもつながり、競合に遅れを取らない体制を構築できます。
チームの連携を強化する
最後に、成果を最大化するためにはチームの連携が不可欠です。UI/UX改善には、デザイン部門だけでなく、開発部門や事業部門も深く関わります。
それぞれの部門が持つ知見を融合させることで、ユーザーにとって使いやすく、かつ事業成果につながる改善が実現します。
例えば、デザイナーが提案するUI案を開発部門が実装可能な形に具体化し、事業部門が収益性やKPIへの影響を検証するなどの連携が求められます。
部門間の情報共有や共通の目標設定を徹底することで、改善施策が一貫性を持ち、成果に直結する取り組みとなるのです。
ユーザー価値を追求するUI/UX改善なら「Proximo」へ
UI/UX改善を本気で成果につなげたいなら、専門家の力を借りるのが近道です。Proximoでは、アプリやWebサイトのUI/UXデザインを専門的に支援し、デザインから開発まで一貫したサービスを提供しています。
デザイナーがクライアントチームの一員として参画し、課題解決や事業成長を見据えた体験設計を共創していくことも可能です。要件の変更や追加にも柔軟に対応可能なため、現場の状況に即した改善をスピーディーに実現できます。
成果に直結するUI/UX改善を目指している企業様は、ぜひ一度、以下からサービスの詳細をご覧ください。
まとめ
UI/UX改善は、ユーザー体験の質を高め、満足度や意思決定を促す重要な取り組みです。そのためには、目的とゴールを明確に設定し、ユーザーニーズを正確に把握した上で、検証と改善を繰り返すプロセスが欠かせません。
さらに、部門横断的なチーム連携を強化することで、施策に一貫性を持たせることが可能になります。自社の成果を高めたい企業は、UI/UX改善を戦略的に進めていきましょう。