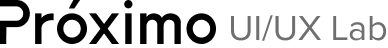プロダクト改善を成功させる!押さえるべき本質と具体的アクションを徹底解説
プロダクト改善は、プロダクトを成長させ、ユーザーに長く愛される存在にするに、継続的に行うものです。
しかし、何をどう改善すべきか、どのようにチームで取り組むべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、プロダクト改善を成功させるために必要な視点や戦略、具体的なアプローチ方法を、実践的な構成で詳しく解説します。
目次
プロダクト改善とは何か?

なぜプロダクト改善が今重要なのか
現在のプロダクト開発の現場では、「改善」という言葉が日常的に使われるようになっています。
しかしながら、その意味を正確に理解し、本質的に価値のある行動に落とし込めている企業やチームは意外と少ないのが実情です。
けれども本来、プロダクト改善とはプロダクトの価値を最大化し、継続的に成長させていくための戦略的な取り組みであり、それがなければ顧客の支持を失い、競合に取り残されるリスクが高まります。
この背景には、ユーザーのニーズがかつてないほど多様化・変化しているという現実があります。
こうした中で、既存のプロダクトを改善し続け、ユーザーにとって「価値があり続ける」状態を維持することが、競争優位性を保つために不可欠なのです。
つまり、プロダクト改善とは単なる作業ではなく、「顧客と事業を成功に導くための戦略」そのものなのです。
プロダクト改善を進めるうえで必要な視点と価値観とは
改善に必要な視座と戦略的思考
プロダクト改善を成功させるためには、日々のオペレーションレベルに留まらず、より高い視座と長期的な戦略思考を持つことが求められます。
多くのプロダクトチームが抱える課題のひとつに、「ユーザーの声を拾っているのに改善がうまく進まない」というものがあります。
その理由のひとつが、目の前の課題に反応することに終始し、プロダクト全体の方向性や価値との整合性を持たずに施策を進めてしまっているからです。
戦略的思考とは、「今やるべきこと」だけでなく、「なぜそれをやるのか」「やることでどう価値が高まるのか」を明確にした上で意思決定を行うことです。
このとき、ロードマップやプロダクトビジョンが強力な道標になります。
また、戦略的思考を持つためには、データ・市場・競合などの情報を常にインプットする姿勢も欠かせません。
ユーザーが変化していれば、必要な改善の方向性も変わっていきます。その変化を感じ取り、タイムリーにプロダクトの方針へ落とし込む感度の高さが、優れたプロダクト改善に直結します。
チームの文化として根付かせる方法
優れたプロダクト改善は、個人の努力だけで実現できるものではありません。
継続的で本質的な改善活動を維持するには、改善の視点や行動が、チーム全体に文化として根付いていることが必要です。
まず重要なのは、「改善は全員の仕事である」という共通認識をチーム全体に持たせることです。
プロダクトマネージャーだけでなく、エンジニア、デザイナー、カスタマーサクセス、マーケティングなど、すべての関係者が「ユーザーの課題を発見し、価値に変える」視点を持つことで、改善の種は組織のあらゆる場所から生まれます。
そのために有効なのが、改善の情報共有を仕組み化することです。
もうひとつ重要なのは、改善に対して「評価される文化」を築くことです。改善は往々にして地味で、直接的に売上に貢献しないこともあります。
ですが、改善がもたらす継続的な価値創出に光を当て、改善に取り組んだ人を称える仕組みを持つことで、メンバーの主体性を引き出すことができます。
成功するプロダクト改善に共通する3つの土台

顧客理解の徹底
プロダクト改善の最も基本的であり、かつ最も重要な土台が「顧客理解」です。
どんなに優れた技術を使っていても、どれだけ美しいUIを設計していても、ユーザーの本質的な課題やニーズを捉えられていなければ、プロダクトはただの自己満足で終わります。
顧客のことを知っているつもりになり、過去の成功体験に依存している状態は、改善の停滞を生みます。
顧客理解とは、単に「要望を聞く」ことではありません。むしろ、表面的な要望に惑わされず、「なぜその要望が生まれたのか」という背景や文脈を掘り下げることが肝心です。
効果的な顧客理解のためには、定性的・定量的の両アプローチを活用すべきです。ユーザーインタビューやカスタマーサポートのログなどからは、顧客の感情や本音を引き出すことができます。
一方で、行動ログやプロダクトの利用データを分析することで、実際にどう使われているのかを客観的に把握できます。この両輪を回すことで、表層的な意見や偏ったデータに流されず、本質的な改善のヒントを見つけることができます。
データドリブンな仮説検証
改善は思いつきや感覚に頼るのではなく、明確な仮説とデータに基づいた検証を繰り返すプロセスであるべきです。
感覚だけで「これがいいはず」と進める施策は、一見スピード感があるようでいて、長期的には非効率であり、チームの学習も停滞します。
仮説検証とは、ある課題に対して「この施策を行えば、こう変化するはずだ」という予測を立て、それを実際のデータで裏付けるプロセスです。
このような仮説とデータに基づいた改善のプロセスを持つことで、失敗しても学びが得られ、次の改善へとスムーズに繋がっていきます。
プロダクト改善の現場でありがちな落とし穴は、「データが溜まっているのに活用されていない」「見るべき数字が定まっていない」という状況です。KPIやOKRなどの指標を明確に設定し、その数値がどの施策にどのような影響を与えているかを継続的に確認することが求められます。
フィードバックループの構築
プロダクト改善が継続的に回り続けるためには、「フィードバックループ」を意図的に設計し、仕組みとして組み込む必要があります。
フィードバックループとは、ユーザーの行動や意見を受け取り、それに基づいてプロダクトを改善し、その結果を再度観察するという一連の流れを指します。このループが回っている状態こそが、改善が機能している証拠です。
一度きりの改善で満足してしまい、ユーザーの反応を収集しないまま次の施策に移る。これは非常に多くのチームで見られる失敗パターンです。
改善の本質は“学習”であり、学習はフィードバックなしには成立しません。ユーザーの声や行動からの気づきを取り込み、改善策を再検討することで、プロダクトは初めて前進します。
これは組織全体の改善力を底上げする、大きな推進力となりプロダクトの成長に繋がります。
プロダクト改善を加速させる4ステップのアプローチ
ニーズ分析と課題設定
プロダクト改善の第一歩は、顧客の本質的なニーズを明らかにし、それを正確に課題として設定することです。
このステップが曖昧なまま進めてしまうと、的外れな施策に工数を投じることになり、改善どころかプロダクトの方向性を誤るリスクがあります。
多くの現場では、「顧客がこう言っているから」という表層的な要望を鵜呑みにしがちですが、実際にはその奥にある“なぜ”を探ることが肝心です。
ユーザーインタビューを設計する際も、「何が不便か」だけでなく、「なぜそのような行動を取ったのか」「本来どうなってほしいのか」といった質問を用意することで、隠れた課題を浮かび上がらせることができます。
課題設定では、収集した情報を整理し、プロダクトチーム全員が共通認識を持てるような形に変換することも重要です。
ジョブ理論(Jobs To Be Done)を活用し、「顧客がこのプロダクトを通じてどんな進捗や成果を得たいのか」という視点でまとめることで、目的と手段を明確に分けた課題設計が可能になります。
正確なニーズ分析と課題設定ができていれば、以降の施策は自然と的を射るものになっていきます。
改善施策の立案と優先順位づけ
適切に課題が定義できたら、次はそれを解決するための具体的な改善施策を立案し、実行可能な形に落とし込む段階です。
まず、施策の立案では、ブレインストーミングや類似事例のリサーチ、競合分析などを通じて、できるだけ多くの選択肢を集めます。
重要なのは、幅広い視点からアイデアを出すこと。エンジニアリング、マーケティング、カスタマーサクセスなど、さまざまな部門の視点を取り入れることで、想像以上にインパクトのある施策が見えてくることもあります。
そのうえで、収集した施策を「実現のしやすさ(工数やリソース)」と「効果の大きさ(ビジネスやUXへの影響)」の2軸で評価するのが一般的です。
よく使われるのが「Impact × Effort マトリクス」です。インパクトが高く、労力が小さい施策から優先的に着手することで、改善の成果を早期に出しやすくなります。
また、優先順位を定める際には、プロダクトのフェーズや組織の戦略と照らし合わせることも忘れてはいけません。
優先順位づけとは、やるべきことを決めるだけでなく、「やらないことを決めること」でもあるわけです。
実装とユーザー検証の繰り返し
施策の実行に着手した段階で重要になるのが、「素早く試し、素早く学ぶ」というアプローチです。
特にプロダクト改善においては、完璧を目指すよりも、仮説の検証を早期に行い、方向修正を可能にする柔軟性が問われます。
改善のアイデアが施策として具体化された後、まずはMVP(Minimum Viable Product)やベータ機能など、小規模な形で一部のユーザーに展開し、反応を観察します。この段階で得られるフィードバックは非常に貴重であり、リリース前に修正を加えることが可能になります。
検証の方法としては、定量的な指標(利用率、エラー率、継続率など)と定性的な意見(アンケート、カスタマーサポートの問い合わせなど)の両方を活用するのが効果的です。
また、検証後は必ず振り返りのプロセスを持つべきです。施策の結果をプロダクトチーム内で共有し、「仮説は正しかったか」「施策は目標に対して十分な効果を出せたか」「改善点は何か」を明確にすることで、次回の改善につなげる学びが得られます。
改善サイクルを継続する体制構築
改善を一過性の取り組みで終わらせず、持続的に回し続けるには、それを支える「体制」と「文化」の整備が欠かせません。
どんなに優れた施策も、継続的な仕組みがなければ、チームの退職や組織変更によって失われてしまいます。だからこそ、改善を“属人化”させず、再現性のあるプロセスとして組織に根づかせることが重要です。
体制構築でまず求められるのは、「改善活動を担う役割と責任の明確化」です。
誰が何を判断し、どのように実行に移すのか。そのフローが曖昧だと、改善案が出ても実行に移されず、機会損失が生まれます。改善タスクを定常業務としてスプリントに組み込む、専任の改善担当者を設けるなど、日常の業務の中に改善活動を“仕込む”ことが有効です。
次に重要なのが「ナレッジの蓄積と共有」です。
過去に実施した施策とその結果、検証のログ、得られた知見などを体系的に記録・共有する仕組みがなければ、同じ失敗を繰り返したり、成功の再現ができなかったりします。
NotionやConfluenceのようなツールを活用し、改善知見を“資産”として残すことが求められます。
さらに、マネジメント層のコミットメントも非常に重要です。
改善が組織にとって“重要視されている活動”であることを経営陣が発信し、リソースや評価に反映させることで、チーム全体のモチベーションや本気度が変わります。
ユーザーの心を掴むプロダクト改善の秘訣
利用体験を最優先に設計する
現代のユーザーは、機能性だけでなく「体験」に高い価値を求めています。
どれだけ多機能であっても、利用体験が煩雑だったりストレスを感じるものであれば、そのプロダクトは使われなくなってしまいます。
プロダクト改善において、「体験設計」を最優先事項として捉えることは、競争優位性の確立に直結します。
体験の質を向上させるには、ユーザーの行動や心理を深く理解する必要があります。オンボーディング、エラーハンドリング、ナビゲーション、フィードバック表示など、ユーザーが画面を操作する全ての瞬間が「体験」を形成しています。
特に初回利用時の印象はその後の継続率を大きく左右するため、必要最小限のアクションで“成功体験”を提供する設計が求められます。
体験設計において重要なのは、UIの美しさではなく“ユーザーの期待と行動とのギャップを埋めること”です。
どこをクリックすればいいか、次に何をすればいいかが明確であること。不要な情報が視界を邪魔しないこと。目的を達成するまでのフローがシンプルであること。これらはすべて、「ユーザーを迷わせない」という設計思想の延長線上にあります。
また、ユーザーからのフィードバックを継続的に取り入れることも体験向上のポイントです。
つまり、「使いやすさ」を突き詰めた体験設計こそが、ユーザーに選ばれ続けるプロダクトの土台になります。機能を増やす前に、まずは既存の体験が最適かを見直すこと。そこから改善の第一歩が始まります。
このUI/UXデザイン支援こそ、Proximoが最も強みを発揮できる分野です。
以下のリンクからUI/UXデザインコンサルティング事例をご覧ください。
継続利用を促すUXデザインとは
ユーザーが一度使って終わるのではなく、繰り返し継続的にプロダクトを使ってくれる状態をつくるには、「UXデザイン」が非常に大きな役割を果たします。
単に初回の体験が良いだけでは不十分で、日々の利用の中で違和感なく、自然に価値を感じ続けられることが重要です。
UXデザインの本質は、ユーザーが“迷わず“ストレスなく”、“期待通りに”行動できることにあります。
これは、視覚的なデザインだけではなく、情報設計やインタラクション、エラーメッセージ、遷移フローなど、プロダクト全体の構造に関わる領域です。
継続利用を促すためには、プロダクトを利用する“動機”や“目的”を設計に反映させる必要があります。
つまり、UXは機能ではなく、ユーザーに提供する“成果”や“意味”にフォーカスすべきなのです。
また、「UXに一貫性を持たせる」ことも重要です。
画面ごとにデザインのトーンがバラバラだったり、操作方法が異なったりすると、ユーザーは混乱し、信頼感を失います。
これを防ぐには、デザインシステムやガイドラインを整備し、全ての機能や画面で一貫した操作体験を提供する必要があります。
プロダクトとユーザーの感情的つながりを作る
機能や利便性を超えて、ユーザーが「このプロダクトが好きだ」と感じるようになると、プロダクトは単なるツールから“パートナー”のような存在へと進化します。
その鍵となるのが、「感情的なつながり」の構築です。プロダクトに対して愛着を持ってもらうには、合理性だけでなく情緒にも訴えかける要素が必要になります。
感情的つながりの構築においては、まず「プロダクトトーン」の一貫性が重要です。
さらに、ユーザーの小さな成功体験を称賛する仕組みも効果的です。
タスク完了時のアニメーションや、進捗の可視化、ポジティブなフィードバックなど、ユーザーが「自分はちゃんと前に進めている」と実感できる仕掛けを随所に設けることで、心理的満足度が高まります。
また、カスタマーサポートやアップデート通知など、ユーザーとの接点一つひとつに“人間味”を込めることで、距離感はぐっと縮まります。
単なるデジタルサービスではなく、「人が作り、支えてくれている」という実感があることで、プロダクトに対する信頼と愛着が強まっていくのです。
感情的つながりは数値化が難しく、つい後回しにされがちな領域です。しかし、この“好き”という気持ちこそが、ユーザーを離れにくくし、口コミや紹介などの自然流入にもつながる強力な要素となります。
意思決定の質を高めるための改善ロードマップ設計法

短期と長期のバランスをとった計画の立て方
プロダクト改善を進める上で最も重要なことの一つは、「どの施策を、いつ、どのような順序で行うか」を戦略的に設計することです。
本質的なプロダクト改善とは、短期的な成果を出しながらも、中長期での成長ストーリーを見据えたアクションを組み立てることに他なりません。
短期的な施策は、効果の即時性や改善サイクルの速度に優れており、ユーザー満足度の向上や定着率改善に直結します。一方で、長期的な施策は、プロダクトの方向性やブランドの構築、競合優位性の確保に欠かせません。
この2つはどちらも重要であり、どちらかを犠牲にするのではなく、計画的にバランスをとることが求められます。
短期と長期のバランスを取ることは、ただの配分ではありません。目の前の改善を着実にこなしながら、同時に未来の価値を設計し続けるという、高度な意思決定です。
この考え方を軸にしたロードマップ設計こそが、プロダクトを持続的に成長させる力になります。
チーム内合意を得るためのドキュメント化の工夫
改善施策を実行に移す上で、もう一つ見落とされがちなのが「チーム内での合意形成」と「そのためのドキュメント化」です。どんなに素晴らしいアイデアも、関係者の理解や納得がなければ前に進みません。プロダクト改善がスムーズに進むチームと、そうでないチームの違いは、意見の衝突ではなく「目的と判断基準の共有ができているかどうか」にあります。
改善のアイデアや背景、狙い、優先度などをチーム全体で共有するには、情報を構造化して文書化することが非常に効果的です。
会議で口頭で説明するだけでは、記憶にも残らず、議論のたびにズレが生じてしまいます。一方で、共通言語となるドキュメントがあれば、意思決定の軸が明確になり、議論も建設的になります。
特に有効なのが、「Why(なぜ)」「What(何を)」「How(どうやって)」の3階層で構成された改善計画書です。
なぜその改善を行うのか(背景や課題)、何を改善するのか(対象機能やKPI)、どうやって進めるのか(スケジュールや担当者)を整理しておくことで、誰が読んでも同じ解釈ができる資料になります。
プロダクト改善に役立つ実践的なフレームワーク集
戦略設計に使えるビジネスフレームワーク
プロダクト改善は感覚や経験則だけで行うには限界があり、戦略的に考えるためには「フレームワーク」が極めて有効です。
特にビジネスの視点を取り入れた改善を行う際には、課題の構造化、意思決定の明確化、優先順位づけなど、ロジックを支える枠組みが求められます。フレームワークは、複雑な状況を整理し、チーム全員の認識を揃えるための“共通言語”とも言えます。
改善ロードマップの優先順位決定には、「SWOT分析」や「Impact × Effort マトリクス」も強力な手法です。
このようなフレームワークを使うことで、議論が抽象論に陥ることを防ぎ、具体的なアクションに落とし込めます。ただし重要なのは「フレームワークありき」にしないこと。目的に応じて柔軟に使い分け、チームの共通認識をつくるための“手段”として活用する意識が大切です。
機能改善に適したUI/UX評価モデル
プロダクト改善では、「どの機能が使われていないのか」「なぜユーザーが離脱しているのか」を把握する必要がありますが、これを感覚で判断すると誤った方向に進むこともあります。
そこで役に立つのが、UI/UXに特化した評価フレームワークです。これらを活用することで、主観に頼らず、客観的にユーザー体験を測定・分析し、改善の優先度を定めることができます。
最も広く使われているのは「ユーザビリティ5原則(ISO9241-11)」です。
これは有効性・効率性・満足度・学習しやすさ・エラーの少なさという5つの観点からUI/UXを評価する枠組みであり、プロダクトの使いやすさを網羅的にチェックすることができます。
また、ヒューリスティック評価(Nielsenの10原則)も、UX改善の初期段階で非常に有効です。
専門家が既存UIを評価し、問題点を洗い出す方法で、設計上の抜け漏れや一貫性の欠如、ユーザーの自由度不足などを発見するのに適しています。これは大掛かりなユーザーテストができない段階でも、比較的低コストで導入可能です。
評価モデルは“診断ツール”のような存在です。
病気の症状を見つけるように、プロダクトの不調を冷静に可視化し、正しい対処を導いてくれます。
改善の優先順位を定量的・定性的に語れるようになることで、意思決定のスピードも精度も高まっていきます。
UI/UXの改善は、プロダクト改善の中でも最もユーザー体験に直結する領域です。フレームワークを使って構造的に評価することで、真に必要とされる改善施策を見極め、ユーザーにとって“心地よい”プロダクトを作ることができます。
社内外のステークホルダーを巻き込むための工夫
部門間の調整で陥りがちな落とし穴とその対策
プロダクト改善を推進していく上で、プロダクトチーム単独で進められることには限界があります。
特にBtoB領域や組織規模の大きい企業では、多様な部門が関わる中での調整が不可避です。
しかし、多くの現場ではこの「部門間調整」がボトルネックになってしまい、改善のスピードや質に大きな影響を与えています。
この課題を解決するためには、まず「目的の共有」と「共通言語の構築」が不可欠です。
改善施策ごとに、その背景・狙い・期待される効果をわかりやすく言語化し、関係者に伝える必要があります。その際、「この改善は〇〇部門にとってもこういうメリットがある」といった形で、部門ごとの視点に翻訳することで、納得感が高まります。
顧客をプロセスに巻き込む共創の手法
優れたプロダクトは、社内で完結して生まれるものではありません。
実際に使うユーザーや顧客を改善のプロセスに巻き込み、共に創り上げていく姿勢が、顧客満足度の向上にも、機能の的確な進化にもつながります。
しかし、多くの企業では、ユーザーの声を「収集するだけ」で終えてしまい、プロセスに「参加してもらう」フェーズには至っていないのが実情です。
顧客との共創の第一歩は、「声を集める場の整備」です。
次に重要なのが、「フィードバックを反映していることの見える化」です。
ユーザーの意見を取り入れた施策が実装された際には、その旨を具体的に発信し、「あなたの意見が反映されました」と示すことで、ユーザーの信頼感と愛着は格段に高まります。
これは機能の完成度だけでなく、“一緒に作っている”という共創感を強く醸成します。
共創のプロセスは、単に情報を得る手段ではなく、ユーザーとの関係性を深めるマーケティング活動でもあります。
共創によってプロダクトが“自分ごと化”されると、ユーザーは単なる利用者ではなく、支持者・提案者・アンバサダーへと変化していきます。
まとめ
プロダクト改善というと、大規模なリニューアルや大胆な機能追加を想像しがちですが、実際には「小さな改善の積み重ね」が大きな成果につながるケースが圧倒的に多いのです。
なぜなら、ユーザーが日々接するプロダクトの“体験”は、無数の小さな接点で構成されているからです。
改善のインパクトは、「改善の大きさ」ではなく「改善の量と質」で決まります。
100点を目指すよりも、80点の改善を早くリリースし、ユーザーからの反応をもとに次の手を打つ。このスピード感と柔軟性が、改善サイクルを加速させ、結果として大きな成果を生み出します。
Proximoでは、UI/UXデザイン支援という形で、企業のプロダクト改善を支援しています。
詳細は以下リンクからご覧ください。
「改善の量と質」をUI/UXデザイン支援のプロと進めていくことは、最も効率の良い部分だと思います。
弊社のUI/UXデザイン実績をまとめております。多くの支援実績がございますので、皆様に事例をご参照ください。
UI/IXデザイン支援により、プロダクト改善をお考え中の方は、一度弊社サービス詳細をご覧ください。