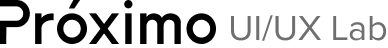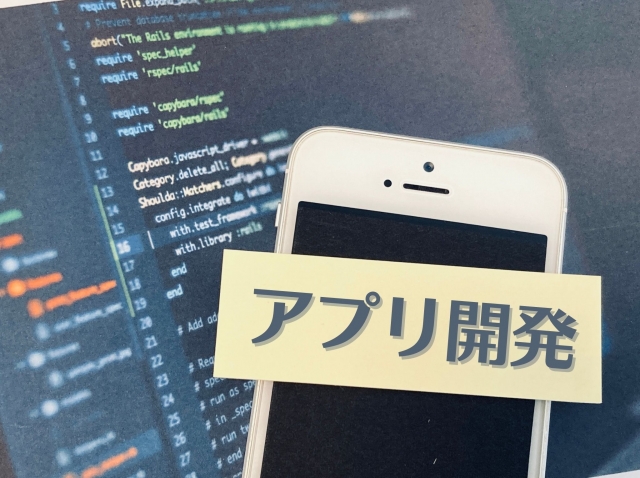社内システムが使いにくい!その瞬間が業務改善の第一歩

日々の業務で、社内システムにストレスを感じていませんか?
多くの企業で導入されている業務支援システムですが、実は“使いにくさ”が原因で業務効率が下がっていたり、社員の不満が蓄積していたりするケースが少なくありません。
今回は、社内システムが「使いにくい」と感じられてしまう原因を掘り下げ、システム刷新のポイントまでを網羅的に解説します。
目次
社内システムが使いにくいと悩む原因を可視化しよう
1. 古いシステムのまま放置されている
現在も業務で使われているシステムが、10年以上前に開発・導入されたまま一度も改修されていないという企業は少なくありません。
このような「レガシーシステム」は、導入当時の業務内容には合っていても、時代とともに変化する業務フローやセキュリティ要件に適応できておらず、利便性・操作性の面で大きなギャップが生じます。
また、技術的な面でも課題があります。古いシステムは最新のOSやブラウザとの互換性が不十分で、動作が不安定になったり、アップデートによって機能が壊れたりすることもあります。
このような状況は、業務効率を著しく損なうだけでなく、社員のモチベーション低下やトラブルの温床にもなりかねませんので、見逃せません。
2. 複数のツールが混在し管理が煩雑
業務のデジタル化が進む中で、1社の中に複数のシステムやツールが乱立している状況はよくあります。
厄介なのは、ツール間での連携が取れていない場合です。たとえば、Aシステムで承認された情報を、別のBシステムに手入力しなければならないという状況が発生すると、単純作業が増え、ミスのリスクも高まります。
現場では「同じ情報を何回も入力するのが面倒」「どのツールに何があるか分からない」といった声が頻繁に上がります。
このような煩雑さが日常化すると、情報の分断や属人化も進み、業務の透明性や効率性が失われていきます。特にテレワークや拠点間連携が求められる時代において、統一された業務基盤がないことは致命的な遅れを生み出します。
理想的なのは、業務の流れに沿ってシームレスに連携する統合型の社内システムを構築することで、情報の一元化と操作の簡略化が実現できます。
3. 利用者への配慮が不足している
多くの社内システムでは、導入や改修の際に「現場の使いやすさ」が後回しにされてしまう傾向があります。
経営層やIT部門の都合、コストや機能優先の判断でシステムが設計される結果、現場の実情に合わない画面構成や操作フローになってしまうのです。
このような設計ミスは、利用者の操作ミスを誘発するだけでなく、「使いにくい」という漠然とした不満の温床になります。その不満が放置されると、やがてシステムに対する信頼を失い、「使いたくない」「紙の方が早い」といった逆行的な行動に繋がることすらあります。
現場で実際にそのシステムを使う社員の声を取り入れること、これは非常に重要なステップです。また、UI/UXに強い開発会社と連携し、ユーザーテストを繰り返すことも有効です。
企業がシステム投資を成功させるためには、「利用者の満足度を高める設計」が前提であることを忘れてはなりません。
使いにくいという第一印象が改善されれば、システムの定着率も向上し、最終的には業務効率・社員満足度・組織の一体感にも良い影響を及ぼします。
Proximoは、UI/UXデザインコンサルティングを行っています。社内で複雑化しているシステムを再構築し、業務効率化に繋げています。
Proximoがどのような形で支援しているのかは、以下のリンクから、ご覧ください。
使いにくい社内システムがもたらすマイナス影響
1. 作業効率が低下する
社内システムが使いにくいと、最も直接的に表れるのが「作業効率の低下」です。1件の処理にかかる時間がわずか数分増えるだけでも、1日、1週間、1カ月のスパンで見れば膨大な時間の損失となります。
このような環境では、本来業務に集中すべき力を余計な操作に割くことになり、生産性の低下は避けられません。
また、システム操作に慣れていない社員ほど、こうした使いにくさの影響を大きく受けやすく、社内に操作方法の属人化が生まれる原因にもなります。
「あの人に聞かないと分からない」という状態は、業務継続性にも悪影響を与え、組織全体としての対応力や柔軟性を損なってしまうわけです。
2. ヒューマンエラーが増える
社内システムの設計が直感的でなかったり、複雑な入力操作が必要だったりすると、ミスが発生する確率は格段に高くなります。
これらのヒューマンエラーは、最初は些細に見えるかもしれませんが、積み重なれば企業の信用や損益にまで影響する可能性があります。
また、操作ミスをした際にその場で修正ができなかったり、エラーメッセージが不親切で原因が分からないまま操作を続けてしまうことも、二次的なミスや大きなトラブルにつながります。
ミスを未然に防ぐためのシステム設計、つまり「間違えようのない操作フロー」や「ガイド付きの入力補助機能」が不足している場合、社員一人ひとりの注意力に依存するしかなくなり、業務リスクが高まってしまうのです。
つまり、ヒューマンエラーを減らすためには、人に頼るのではなく、システムそのものを“エラーしにくい仕組み”へと改善する必要があります。
3. 社内ストレスや離職にもつながる
システムの使いにくさは、ただ単に業務のやりづらさにとどまらず、社員の心身のストレスに直結する深刻な問題です。
実際、社内の離職理由として「業務環境が整っていない」「非効率なシステムに疲れた」という声が挙がることもあり、単に待遇や仕事内容だけが原因ではないケースも多いのです。
新人や中途採用者にとっても、最初に触れる社内システムが「使いにくい」と感じると、「この会社は古い体質なのでは」「成長できなさそう」と判断されてしまい、早期離職の引き金になる可能性すらあります。
企業が人材確保や社員定着を重視するのであれば、働く人がストレスなく業務に取り組める環境整備は必須条件と言えます。
社内システムを根本から見直すにはどうすればよいか
1. 業務プロセスに合った要件定義を行う
社内システムの再構築や改善において、最初に重要になるのは「業務に合った要件定義」を行うことです。
多くの失敗事例では、IT部門や外部ベンダーが一方的に要件を決めてしまい、現場の実態やニーズと乖離した仕様になってしまうという共通点があります。
結果として、機能は豊富なのに実際には「使われない」システムになり、コストばかりがかさんでしまいます。
業務プロセスに合った要件定義を行うには、まず現状の業務フローを正確に把握することが必要です。現場の担当者と対話を重ね、どこに課題があるのか、何が無駄で、どこを効率化すべきなのかを洗い出すことで、本当に必要な機能が見えてきます。
この視点が欠けると、再び「時代遅れで使いにくいシステム」を抱えることになりかねません。正しい要件定義は、すべての工程の土台となるわけです。
2. UI/UXの設計から見直す
業務システムは、その機能性も重要ですが、実際に使われる現場にとっては「使いやすさ」がすべてと言っても過言ではありません。
複雑でわかりにくい画面設計は、せっかくの機能を台無しにし、操作ミスや業務停滞を引き起こします。だからこそ、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)を意識した設計が欠かせません。
具体的には、「使用頻度の高いボタンを目立たせる」「画面の遷移を最小限に抑える」「説明文や入力例を表示する」といった工夫が必要です。
システム開発の現場では、「見た目は後回し」とされがちですが、実際にはUI/UXがシステム活用率や満足度を大きく左右します。
デザインの専門家と連携し、ユーザー行動を想定したプロトタイプを検証しながら進めることで、より実用的で好まれる設計が可能になります。
最終的に、どれだけ優れたシステムを構築しても、それが“使いたくなる”ものでなければ意味がありません。だからこそ、UI/UXの設計にこだわることは、「投資を最大化」するための必要条件なのです。
Proximoは、UI/UXデザインコンサルティングを行っています。業務で活用している社内システムをよりわかりやすい画面や操作性向上などを行い、効率化に繋げています。
Proximoが支援してきた企業事例を以下のリンクから、ご覧ください。
3. 定期的なフィードバックサイクルを設ける
一度導入したシステムを「完成」と見なして放置するのは、大きな間違いです。
現場の業務や市場環境は常に変化しており、システムもそれに応じて進化し続ける必要があります。そのためには、導入後の運用フェーズにおいても「定期的なフィードバックサイクル」を設けることが不可欠です。
「こんな意見が出たので、次回はここを改善します」と明確に伝えることで、社員の信頼と参画意識が高まり、システムに対する理解と定着率も向上します。
改善の余地を常に認識し、少しずつでも手を加えていく姿勢が、結果的にシステムの完成度を高め、長期的な満足度につながります。フィードバックサイクルを“習慣”として定着させることが、使いやすく、変化に強い社内システムを育てる鍵となるのです。
システム開発会社に任せる前に確認すべき重要ポイント
実績・専門性・対応力を比較検討することがカギ
社内システムの改善や刷新を外部のシステム開発会社に依頼する場合、その選定は極めて重要な意思決定になります。
一見するとどの会社も同じように見えるかもしれませんが、実際には得意分野や対応スタイル、開発手法などに大きな違いがあり、その選択次第でプロジェクトの成果が左右されると言っても過言ではありません。
だからこそ、安易な価格比較や知名度だけで判断せず、「自社に本当に合う会社かどうか」を見極める必要があります。
まず確認すべきは、過去の開発実績です。単に「多くの開発経験がある」ではなく、「同じ業界」「同じ業務プロセス」「同じ規模感」のプロジェクトに携わった経験があるかどうかが重要です。
また、同様の課題を解決した事例があるかどうかを確認することで、信頼性がぐっと高まります。
次に重視すべきは、その会社の「改善力」と「対応力」です。
ただ開発をするだけでなく、課題の整理から要件の明確化、導入後のアフターサポートに至るまで、総合的に対応できる体制があるかどうかを確認しましょう。
また、見積もりや提案書の内容にも注目するべきです。
丁寧に現場の状況をヒアリングした上で、課題に対する明確なアプローチや解決策を提示してくれる会社であれば、信頼して任せることができます。
自社の課題にしっかりと向き合い、誠実かつ柔軟に対応してくれるパートナーを見つけることが、システム改善プロジェクトの成功において最も大切なポイントです。
従業員が「使いやすい」と実感するシステムを作るには
利用者視点で設計されているかどうかが最重要
社内システムの本来の目的は、業務の効率化と正確性の向上にあります。しかし現場で実際にそのシステムを使う従業員が「使いにくい」と感じてしまえば、その目的は達成できません。
どれほど高機能なシステムであっても、使いこなされなければ無意味です。その鍵となるのが、「利用者視点での設計」です。
実際の現場では、システム開発の初期段階から「何が便利なのか」「どんな点に不満を感じているのか」といった従業員の声を拾い上げることが非常に効果的です。
使用頻度の高いメニューをトップ画面に配置したり、入力項目を絞ったりすることで、作業ストレスは格段に減ります。
こうしたプロセスを通じて、“開発者中心”ではなく“利用者中心”の視点が浸透していきます。
さらに、「自分たちの声が反映されている」と従業員が感じることで、システムへの信頼感が高まり、使い続けようという意識が強くなります。
従業員が「これなら使いたい」と思えるシステムにするためには、設計段階から徹底的に利用者視点を持つことが不可欠です。
トレーニングとサポート体制が「使いやすさ」を継続させる
社内教育とマニュアル整備が重要なポイント
社内システムを刷新した直後に「やっと完成した」と安心する企業は少なくありませんが、実は本当の勝負はそこから始まります。
どれだけ使いやすいシステムを開発しても、それを正しく使いこなす知識と習慣が社内に根付かなければ、システムの価値は発揮されません。つまり、システムの“使いやすさ”は設計だけでなく、その後の運用支援、特に教育とサポート体制によって維持・向上していくのです。
さらに、システムを活用する上で欠かせないのが、わかりやすいマニュアルやFAQの存在です。
すべての社員が同じレベルのITスキルを持っているわけではありません。だからこそ、「誰が読んでも迷わず理解できる」言葉で書かれた、視覚的にわかりやすいマニュアルの整備が必要です。
加えて、マニュアルは一度作ったら終わりではなく、システムのバージョンアップや運用変更に応じて、定期的に更新することも重要です。
また、導入後には「ちょっとした質問ができる場」があるかどうかが、システム定着の鍵を握ります。
チャットサポート、Q&Aフォーラム、定期的な社内勉強会など、小さな疑問をすぐに解決できる仕組みがあるだけで、社員の心理的ハードルは大きく下がります。これにより、「聞きづらい」「調べるのが面倒」という理由でシステム活用を諦める状況を防ぐことができます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)との関連性
業務改善と連動したシステム見直しの必要性
社内システムが「使いにくい」と感じられる背景には、単なるツールの古さや操作性の問題だけでなく、企業の変化にシステムが追いついていないという根本的な問題が潜んでいます。
これを放置したままでは、いくら新しいツールを導入しても、真の改善にはつながりません。そこで重要になるのが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という視点です。
また、DXを推進する過程では、既存システムの見直しが避けられません。
多くの企業では、複数の部署でバラバラのシステムを使っていたり、データがサイロ化していたりと、情報共有や全体最適が阻害されている状況にあります。
こうした問題を解消するには、全社視点で業務を俯瞰し、部門間の連携を前提にした統合的なシステム設計が求められます。これにより、業務のムダやミスが減り、意思決定のスピードと正確性が向上します。
さらに、DXの実現にはテクノロジーだけでなく「人」の側面も重要です。どれだけ優れたシステムを導入しても、それを使いこなすためのリテラシーや、変化を受け入れる組織文化がなければ、定着せずに失敗に終わる可能性があります。
つまり、「使いにくい社内システム」の改善を起点に、業務そのものの見直し、部門間の連携強化、そして組織の体質改善へとつなげていくことが、DX推進の本質です。
社内の声を拾い上げる「聞く姿勢」が改善の出発点
利用者アンケート・ヒアリングでニーズを発見
社内システムの改善に取り組む際、多くの企業がシステムの仕様や機能ばかりに目を向けてしまい、肝心の「現場の声」に耳を傾けることを忘れてしまいます。
しかし、システムを日常的に使っているのは現場の従業員です。現場に寄り添わない改善施策では、どれだけ優れた技術や機能を投入しても、結局「使いにくいまま」「現実と合っていない」という状態に陥ってしまいます。
だからこそ、改善のスタートラインとして「従業員の本音を知ること」が何よりも重要です。
アンケートやヒアリングを行い、机上の議論では得られない“現場のリアル”であり、最も信頼できる改善指針になります。
また、ヒアリングは「声を聞くだけ」の場ではなく、社員にとっても、「自分の意見が受け止められている」と実感できる場であり、システム改善への主体的な参加意識を高める効果もあります。
単なるシステム改修にとどまらず、社内のコミュニケーション活性化や組織風土の改善にもつながっていくのです。
システム改善を成功させるには、「作る」ことよりも「知る」ことが先です。その聞く姿勢こそが、形だけでない本質的な業務改善の第一歩となるのです。
まとめ
日々の業務の中で、「このシステム、なんだか使いにくい」と感じたことがある方は少なくありません。
その違和感を放置したまま業務を続けてしまうと、効率の低下やミスの発生、さらには従業員のモチベーション低下といった、さまざまな悪影響を引き起こします。
特に近年は、業務の多様化・スピード化が進んでいるため、システムの“使いやすさ”は企業の競争力に直結する重要な要素となっています。
これらをProximoでは、内製化研修でもUI/UXデザイン支援を行なっています。
研修内容は大きく2種類あります。
・基礎研修
UI/UXデザインの基本的な考え方やプロセスを学ぶための座学を実施。デザイン原則やユーザビリティ向上に役立つ知識を提供します。
・実践演習
実際のプロジェクトを題材にした演習を通じて、学んだ知識を実践に活かせるスキルを養います。UI/UXデザインをプロジェクトに適用する方法を学びます。
企業のニーズに合わせてカスタマイズする形で研修をご用意しております。
財務や企画に携わる社員や経営層も含む全社員様向けに「基礎知識編」、デザインを学ばれたい希望者の方向けに「実践編」、実プロダクトをテーマとして扱う「実践演習」という3種類の研修を実施しました。
従業員教育の仕組みづくりや内製化にご興味のある方は、以下から詳細をご覧ください。