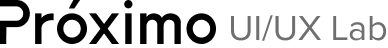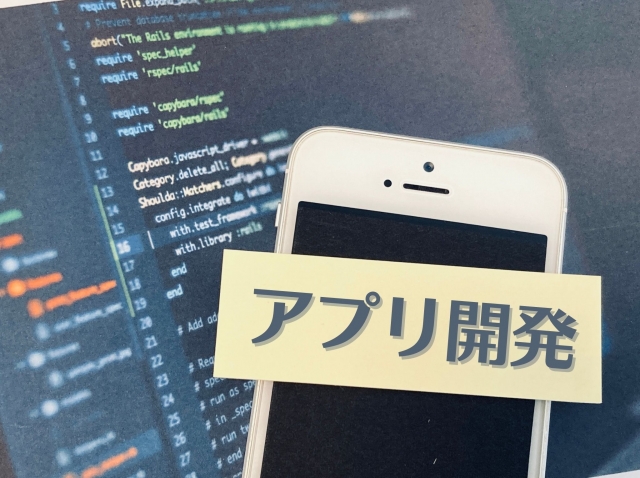デザイン経営で企業の未来を切り拓く?必要な視点と実践
近年、デザインを経営に統合する「デザイン経営」という考え方が注目を集めています。
しかし、「何から始めれば良いのか」「本当に効果があるのか」といった不安を抱える企業も少なくありません。
今回は、デザイン経営の定義から具体的な導入方法、成功事例、人材育成までを幅広く解説し、お読みくださる皆様が自社で実践できるようになるための視点とヒントを解説します。
目次
デザイン経営が今注目されている理由

かつて、企業の競争力は「モノづくりの質」と「コスト競争力」によって測られていました。
大量生産・大量消費の時代においては、優れた製品を安価に提供できることが最大の強みだったからです。しかし、時代は変わりました。
市場は成熟し、顧客の価値観は多様化しています。今や製品の機能やスペックだけでは選ばれない時代に突入しているのです。そうした背景のもと、「デザイン経営」が大きな注目を集めるようになりました。
そもそも、デザインという言葉は一般的に「見た目」や「美しさ」を連想させがちです。しかし、近年のビジネスシーンにおいて「デザイン」は、顧客体験全体の設計や、ブランドの世界観を構築するための思考プロセスを意味するようになってきました。単なる表層的な装飾ではなく、事業の本質的な価値を定義し、伝えるための手段として位置付けられているのです。
実際、特許庁や中小企業庁は「デザイン経営」を推進し、経営戦略におけるデザインの重要性を各地で啓発しています。
これにより、地域に根ざした企業であっても、独自の価値観や文化を強みに変えることで、他社との差別化が可能になるという認識が広がりつつあります。
今後、ますます不確実性が高まる社会の中で、企業は生き残りをかけて変革を求められます。その変革の中心に、「意味を設計する」力が求められる時代が到来しています。
そこで必要とされるのが、まさに「デザイン経営」という考え方です。
デザイン経営の定義とビジネスへの意義
デザイン経営という言葉がビジネスの現場で使われるようになってから、まだそれほど年月は経っていません。しかし、その考え方は今や世界中の先進企業の戦略の中核を担うまでに進化しています。
表面的なブランディングや見た目の美しさにとどまらず、顧客との関係構築、製品・サービスの体験設計、企業文化の醸成にまで影響を及ぼす「経営手法」として定義されるようになったのです。
デザイン経営とは、経営層がデザインの重要性を深く理解し、意思決定の中心にデザインの考え方やプロセスを組み込むことで、組織の価値創造力を高める経営アプローチです。
単に「デザイナーを雇う」だけではありません。企業活動全体において、ユーザー視点に立って課題を見つけ、創造的に解決していく文化を根付かせることが目的です。これはビジネスにおいて大きな変化をもたらします。
ブランドが提供する世界観に共感し、自分の価値観と一致する体験を求めて選ぶという行動が主流になっています。これを設計し、届けるのが「デザインの役割」であり、それを全社的に実践するのが「デザイン経営」です。
企業がデザイン経営を導入する最大の目的は、短期的な利益ではなく、中長期的なブランド価値を構築できる点にあるでしょう。
さらに、デザイン経営の特徴は、「形のない価値」に焦点を当てる点にあります。
結局のところ、ビジネスにおける競争優位性は、製品の性能や価格だけでは持続しません。
模倣されにくく、感情的なつながりを生むブランド体験こそが、現代における企業の真の競争力となるのです。そして、それを設計し、経営に組み込んでいくための手段が「デザイン経営」なのです。
経営者がデザインの価値に気づき、戦略的に活用することで、企業はより強く、しなやかに、社会とともに成長していくことができると考えます。
デザイン経営がもたらす具体的な効果
企業が競争環境の中で生き残り、成長を続けていくには、他社にはない独自の価値を提供し続ける必要があります。
従来は、価格や性能といった機能的価値が差別化の要でしたが、現在の市場ではそれだけでは不十分です。顧客の選択基準は、「どのような体験ができるか」「その企業に共感できるか」といった情緒的・感覚的な価値にシフトしています。ここにデザイン経営がもたらす力があります。
デザイン経営を導入することで、まず明確に実感できる効果の一つが「ブランド価値の向上」です。
たとえば同じ商品でも、デザインによって使用感や印象、満足度は大きく変わります。良質な体験を継続的に提供する企業は、「このブランドなら安心」「このサービスには意味がある」と顧客に認知され、信頼と愛着を育むことができます。これは一度きりの購入にとどまらず、リピーターやファンを生み出す力へとつながります。
統一感があることで、企業の信頼性は飛躍的に高まり、選ばれる理由が「価格」ではなく「共感」や「価値観」になるのです。
次に挙げられるのが「社内のイノベーション促進」です。デザイン経営では、ユーザー視点を起点にした課題解決が求められます。
これにより、社員一人ひとりが顧客に向き合い、「なぜこのサービスは選ばれているのか」「どのような体験が求められているのか」といった問いを日常的に考えるようになります。この思考習慣こそが、現場からの発案を増やし、従来の枠にとらわれないアイデアの土壌を育てます。
さらに、デザイン経営には「意思決定の質を高める」という側面もあります。
アイデアを図やプロトタイプとして可視化しながら議論を進めることで、方向性のぶれや無駄な手戻りを減らし、より早く的確な判断が可能になるのです。これは、時間とコストの削減にも直結する重要な効果です。
このように、デザイン経営がもたらす効果は単なる見た目の改善にとどまらず、ブランド構築、組織変革、イノベーション創出、意思決定の質向上といった、あらゆる経営活動に好影響をもたらします。これらが総合的に作用することで、企業は市場において強く、しなやかに、そして持続可能に成長していくことができるのです。
ProximoはUI/UXデザイン支援を行うプロです。
コーポレーションサイトやアプリのデザインを、企画から開発までチームで行っております。
以下のリンクにProximoの、UI/UX支援事例を掲載しております。一度ご覧ください。
デザイン経営を成功させる3つの要素
デザイン経営を企業戦略に取り入れても、それが効果を発揮するとは限りません。ただ導入するだけでは、デザインは単なる装飾にとどまり、企業の根本的な競争力にはつながりません。
成功している企業の共通点を分析すると、そこには「リーダーシップ」「組織文化」「デザインリテラシー」という三つの要素が一貫して存在しています。
まず、第一に必要なのが「リーダーシップ」です。
企業のトップがデザインの重要性を深く理解し、経営戦略の中核に位置づけることが求められます。経営者自らがビジョンを持ち、デザイン的思考の必要性を社内に強く発信することで、初めて全社的な意識改革が始まります。
リーダーが先頭に立ち、「なぜ今、デザイン経営が必要なのか」を語り続けることで、社員の意識も変わり始めるのです。
次に挙げられるのが「組織文化との統合」です。
デザイン経営は一過性のプロジェクトではなく、企業の根幹に根付く文化であるべきです。そのためには、既存の企業文化と融合し、従業員の行動様式や意思決定プロセスに自然とデザイン的視点が組み込まれている状態を目指す必要があります。
三つ目の要素は「デザインリテラシーの向上」です。
デザインリテラシーとは、単にデザインの知識や技法を知っているという意味ではなく、デザイン的な思考――つまり課題を発見し、共感をベースに解決策を創造する力を指します。
これはデザイナーだけに求められるものではなく、マーケティング、営業、開発、バックオフィスなど、あらゆる職種の人材が持つべき共通の能力です。。
この三要素が揃って初めて、企業の中でデザインが真に機能し始めます。逆に言えば、いずれかが欠けている状態では、デザインの力を十分に発揮することは難しいでしょう。
これができてこそ、企業は自らの存在価値を高め、持続的な成長を実現できるのです。
中小企業におけるデザイン経営の導入ポイント

日本の企業の99%以上を占める中小企業にとって、限られた人員や予算の中で他社と差別化し、持続可能な成長を実現するのは非常に大きな課題です。
だからこそ、大企業以上に「少ない投資で最大の成果を生む」戦略が求められます。
そのカギとなるのが、デザイン経営です。中小企業こそ、デザイン経営を柔軟に、かつスピーディに取り入れることが可能なポテンシャルを秘めているのです。
多くの経営者が「デザインはお金がかかる」「専門家がいなければできない」といった先入観を持っています。
しかし、デザイン経営とは高額なデザイナーを雇うことではなく、ユーザー視点を軸に経営判断を行い、製品・サービスやブランドの価値を最大化する思考のことです。むしろ、少人数の意思決定で企業が素早く動ける中小企業にとって、デザイン経営の導入は非常に相性が良いアプローチなのです。
最初は専門家を呼ばずとも、既存の社員と「顧客が本当に求めているものは何か」を考える場を設けることから始めるとよいでしょう。これは費用ゼロでできる、最も基本的で重要なデザイン経営の第一歩です。
デザイン経営は、一部の先進企業だけの特権ではありません。
「顧客に選ばれる理由」を明確にし、それを一貫した体験として提供することで、価格競争に巻き込まれず、独自の価値で支持される企業へと変貌を遂げることができるのです。
つまり、今ある資源をどう活かすかを見直し、ユーザーにとっての価値を再設計すること。それこそが中小企業にとってのデザイン経営の真髄です。
大胆に始める必要はありません。小さく始め、成果を実感しながら徐々に広げていく。この地に足のついたアプローチこそが、変化の激しい時代を生き抜く中小企業にとっての最良の選択となるのです。
デザイン経営における実践的アプローチ
デザイン経営を本格的に推進するためには、抽象的な理念や理想論だけではなく、具体的な実行策が不可欠です。
どんなに素晴らしいビジョンを掲げても、現場で機能しなければ意味がありません。だからこそ、企業の中でどのようにデザイン経営を「仕組み」として実装していくかが重要です。
まず最初に挙げたいのが、「経営チームにデザイナーを配置する」ことです。
これは、単にデザイン業務を外注するのではなく、デザイナーが経営意思決定の場に同席し、経営戦略の立案段階から関与することを意味します。
従来の組織では、デザインは製品完成後の装飾やマーケティング段階で求められる機能でしたが、今後は最上流からデザインの視点を取り込む必要があります。デザイナーが経営陣と対話を重ねることで、ユーザー体験やブランド価値といった要素を事業計画の段階から設計できるようになるのです。
次に重要なのが、「顧客の潜在ニーズを捉えるデザイン手法の活用」です。
デザイン経営では、明確なニーズに応えるだけでなく、顧客自身も気づいていない「無意識の欲求」や「不満」を見つけ出す力が求められます。
そのために活用されるのが、ユーザーインタビュー、ペルソナ設定、カスタマージャーニーマップなどの手法です。
さらに、実践的なアプローチとして有効なのが、「デザイン経営専門の組織やチームを設ける」ことです。
これはプロジェクト単位でも構いませんが、経営と現場をつなぐ橋渡し役としての機能が非常に重要です。組織横断的に動ける小さなチームを設置し、各部門と連携しながらデザイン的な視点を各所に注入することで、自然と社内全体に「ユーザー中心」の視点が広がっていきます。
これらのアプローチを機能させるには、部分的な実施では不十分です。あくまで「企業文化」として、デザインを業務の中に自然と取り込んでいく必要があります。
デザイン経営を推進する企業の多くは、会議資料をビジュアルベースで構成したり、定例会議に顧客の声を必ず取り入れたりと、日常のオペレーションにまでデザイン的な工夫を取り込んでいます。こうした地道な取り組みの積み重ねが、最終的にブランド力やイノベーション力として表れるのです。
デザイン経営に役立つ支援ツールと制度
デザイン経営を本格的に導入しようとする企業にとって、初期段階での「何から始めればよいのか」という不安は避けられません。
特に中小企業の場合、自社に専門知識やノウハウがなく、社内リソースも限られているため、外部の支援やガイドラインが不可欠です。
そこで活用できるのが、行政や関連団体が提供するデザイン経営支援ツールや制度です。これらをうまく活用すれば、初めてでも無理なく段階的にデザイン経営を実行に移すことができます。
最も代表的な支援ツールとして知られているのが、特許庁が提供する「デザイン経営コンパス」です。
これは、企業が自社のデザイン経営の成熟度を自己診断し、どの領域に課題があるのかを可視化するためのフレームワークです。大企業・中小企業を問わず、デザイン経営の導入・推進を検討している組織にとって、現在の立ち位置を理解する手がかりとして非常に有効です。
設問に回答していくだけで、ビジョン共有、組織体制、プロセス設計、成果の測定といった各要素の状況が明らかになり、優先的に取り組むべき課題が見えてきます。
加えて、「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」も極めて実用的な資料です。
これは中小企業向けに特化しており、難解な理論よりも実際の導入プロセスや失敗・成功事例、Q&Aなどが豊富に掲載されています。
業種ごとの実践例も多く、「自社ではこの方法が使えそうだ」と具体的なアクションに落とし込めるような内容になっているため、導入の初期段階で大きな助けとなります。
これらの支援ツールや制度の価値は、単に「知識を得る」ことではありません。重要なのは、それらを実際の経営判断や施策に「活用する」ことにあります。
ProximoでもUI/UXデザインコンサルティングを通して、経営の支援を行っております。ご興味ある方は一度弊社HPからお問い合わせください。
デザイン経営を推進する人材と組織づくり
どれほど優れた戦略や支援ツールがあっても、それを実行する「人」と「組織」が伴わなければ、デザイン経営は機能しません。
実際、現場での取り組みが形骸化してしまう要因の多くは、「推進する人材がいない」「社内の体制が整っていない」ことにあります。
だからこそ、デザイン経営を軸に据えた変革を成功させるには、人材の確保と育成、そして組織的な支援体制の構築が不可欠です。
まず、組織づくりの観点から見ると、専任のデザイン経営チームやプロジェクト推進室を設けることが効果的です。
この推進組織には、デザインに関する専門性を持った人材が必要不可欠です。しかし、それだけでは足りません。重要なのは、「ユーザー視点で考え、社内外と円滑にコミュニケーションをとり、経営戦略に翻訳できる力」を持った人材です。
とはいえ、こうした人材は外部からの採用だけで賄えるものではありません。むしろ、自社の文化や価値観を深く理解した既存社員を育て、段階的にデザインリテラシーを高めていくアプローチのほうが、長期的には定着率も高く、効果的です。
組織全体でデザイン経営を進めていくには、トップダウンとボトムアップの両輪が必要です。経営者が明確なビジョンを掲げ、推進組織が各部門と連携し、現場の社員が主体的に考え、行動する。このような体制が整ってこそ、デザイン経営は単なる取り組みではなく、「企業文化」として根付いていきます。
例えばProximoでは、企業向けに以下のような研修内容を提供しています。
・基礎研修
UI/UXデザインの基本的な考え方やプロセスを学ぶための座学を実施。デザイン原則やユーザビリティ向上に役立つ知識を提供します。
・実践演習
実際のプロジェクトを題材にした演習を通じて、学んだ知識を実践に活かせるスキルを養います。UI/UXデザインをプロジェクトに適用する方法を学びます。
そのほか、企業のニーズに合わせてカスタマイズしたUI/UXトレーニングを提供しており、企業内でのデザインスキルの内製化もサポート可能です。
従業員教育の仕組みづくりや内製化にご興味のある方は、以下から詳細をご覧ください。