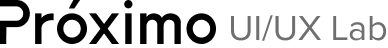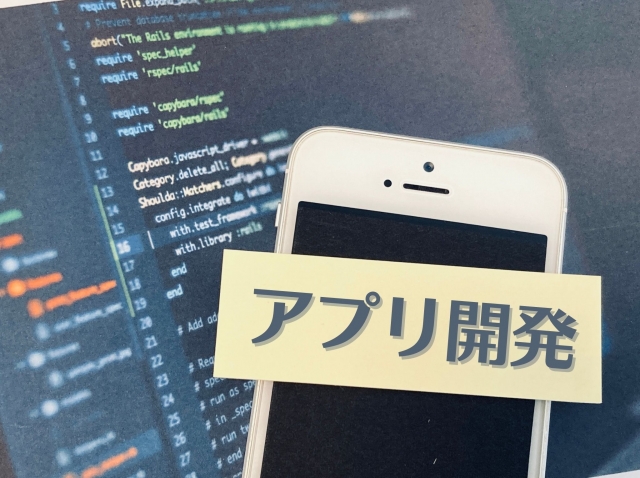【完全ガイド】デザイン思考とは何か?深掘りして実践に活かす
「デザイン思考」は、今や多くの企業や組織が注目しています。それは単なるデザインの手法ではなく、ユーザーの視点に立ち、本当に必要とされる価値を生み出すためのアプローチだからです。
今回は、デザイン思考とは何か、そのプロセスやメリット、実際の事例までをわかりやすく解説します。
目次
デザイン思考とは?

デザイン思考とは、単なる「デザイン業務の手法」ではなく、問題解決のための普遍的な思考フレームワークのことです。
人間中心設計という考え方を根底に持ち、観察や共感を通じて課題を抽出し、その解決策を創造的に導き出します。
このアプローチは、従来の論理思考や効率性を重視するビジネスモデルではすくい取れなかった「潜在的なニーズ」を形にすることを可能にします。
現代社会では、技術革新のスピードが増し、選択肢が豊富であるにも関わらず「本当に必要な価値」が見えにくいという課題が生じています。
そこで重要になるのが「人はなぜその商品を手に取るのか」「どのような感情が購買や行動の背後にあるのか」を探る姿勢です。デザイン思考は、まさにその問いに応える思考法として注目されてきました。
デザイン思考は「ユーザーに寄り添い、その未充足な欲求を発見して形にする」ことに重点を置きます。
そのため、論理の厳密さだけでは解決できない現場の課題や、アート的感性だけでは事業化できないアイデアを現実的に橋渡しする役割を果たすのがデザイン思考です。
「デザイン経営」との違いは、以下のリンクにある、デザイン経営の詳細を知っていただき理解していただければと思います。
参考記事:デザイン経営で企業の未来を切り拓く?必要な視点と実践
デザイン思考が注目される背景
デザイン思考が注目を浴びる背景には、時代の変化と人々の価値観の多様化があります。
かつては「安く、早く、大量に」という効率重視の時代がありましたが、工業製品やサービスは機能的価値を満たすことで十分に市場で成功できたのです。
しかし、現代はすでに物質的な充足が当たり前となり、消費者は「機能」だけでなく「体験」や「意味」を求めています。
こうした変化は企業活動にも直結します。従来の市場調査やデータ分析だけでは、ユーザーが言語化できない不満や欲求を捉えきれません。
そのため、多くの企業がユーザーを実際に観察し、日常生活の中で「言葉にされない課題」を掘り起こす必要に迫られています。デザイン思考は、まさにそのプロセスを体系化した手法として評価されています。
デザイン思考が必要とされるのは「供給過多の時代において真に求められる価値を見つけ出すため」です。社会の変化に対応する力として、単なるブームではなく持続的に活用されるべきアプローチだと言えます。
アート思考や論理思考との違い
デザイン思考を理解する上で、しばしば比較されるのが「アート思考」と「論理思考」です。この違いをお伝えします。
まず論理思考は、問題を因数分解し、順序立てて整理し、最も合理的な解を導くことを目指します。これは企業経営や戦略策定において強力な武器となりますが、前提条件が固定されている場合に限られる傾向があります。
一方、アート思考は既存の枠に囚われず、個人の感性や内発的な問いを起点に新しい視点を生み出すものです。芸術作品の創作過程のように「必ずしも実用性を前提としない」という点が特徴です。そのため大胆で独創的なアイデアを生みますが、現実的に実装する難しさも伴います。
そこで、デザイン思考は、この二つの間に位置する存在だといえます。
ユーザーの声や行動を観察し、それをもとに具体的な課題を定義する点では論理的ですが、その課題に対する解決策を発想する段階では自由度を重視し、アート的な柔軟性も取り込みます。つまり、論理思考とアート思考の「架け橋」となり得るのです。
実際、デザイン思考のプロセスには「定義」と「発想」という両面があります。定義の段階では論理思考の力が求められ、発想の段階ではアート的な直感力が発揮されます。単なるアイデアで終わらず具体的な成果に繋げることが可能になるのがデザイン思考でしょう。
デザイン思考の5段階プロセス

デザイン思考を実践的に運用するためには、そのプロセスを体系的に理解することが欠かせません。
代表的な流れは「共感・定義・発想・試作・テスト」の5段階です。
これらは直線的に一度だけ進むものではなく、必要に応じて何度も行き来しながら精度を高めていく循環型のアプローチです。
共感:ユーザー理解の出発点
最初のステップである「共感」は、デザイン思考の根幹を成す重要なプロセスです。
ここでは、アンケートや数値データだけでは見えてこない、ユーザーの感情や行動の背景にある動機を深く理解することが求められます。
観察やインタビューを通して、言語化されない不便や期待を掘り起こすことが大切です。このプロセスを丁寧に行うことで、後のステップでの課題定義の精度が大幅に向上します。
定義:課題を明確化するプロセス
共感によって得られた情報を整理し、解決すべき本質的な課題を言葉に落とし込むのが「定義」の段階です。
ここでは、表面的な要望に引きずられず「何が本当に解決されるべき問題か」を見極める必要があります。
課題を適切に定義できれば、解決策の方向性は自然と絞り込まれ、次の発想段階でのアイデアの質も格段に高まります。
発想:多様な視点からアイデアを広げる
課題を定義した後は、その解決策を生み出すための「発想」の段階に入ります。
ここで重要なのは、数を意識して幅広くアイデアを出すことです。最初から完璧な案を探すのではなく、自由な発想を奨励し、批判を控えることで、多様な視点が集まりやすくなります。
多様性を持つチームで発想を行えば、個人の思考の枠を超えた新しい解決策が浮かび上がる可能性が高まります。
このプロセスでは質より量を優先し、その後の試作で実現性を検証する流れが理想的です。
試作と検証:形にして学ぶアプローチ
発想されたアイデアを具体的に形にする段階が「試作」です。
ここで求められるのは完成度ではなく、スピードと柔軟性です。紙のスケッチや簡単なモックアップなど、小規模で低コストな方法で構いません。
実際に形にすることで、頭の中だけでは見えなかった課題や改善点が浮き彫りになります。さらに、ユーザーに触れてもらい直接フィードバックを得ることで、実際の使用感に基づいた修正が可能になります。
試作とテストを繰り返すことでアイデアは徐々に洗練され、現実のニーズに即した解決策へと成長していきます。これは「失敗を恐れず学ぶ」というデザイン思考の精神を象徴するプロセスです。
デザイン思考がもたらす3つのメリット
デザイン思考を導入することで、組織やプロジェクトには多くのメリットがもたらされます。
それは単に新しいアイデアを得るだけでなく、組織文化やチームの働き方にまで影響を及ぼします。
イノベーションを創出しやすい環境をつくる
デザイン思考の大きな魅力は、イノベーションを生み出すための「仕組み」を組織に根付かせられることです。
従来の発想法では、過去の成功体験や市場の常識に縛られやすく、革新的なアイデアは埋もれてしまいがちでした。
しかしデザイン思考では、共感を起点とするため「まだ誰も気づいていない課題」や「既存の枠では捉えきれない価値」に焦点が当たります。
これが新規事業や新製品の開発につながる大きな突破口となります。デザイン思考は、こうした新しい市場機会の発見を自然に促すのです。
チームの協働とコミュニケーションが促進される
デザイン思考は個人の作業ではなく、チームで取り組むことを前提としています。
多様なバックグラウンドを持つメンバーが共に課題を観察し、意見を出し合うプロセスは、従来のトップダウン型の意思決定とは異なり、双方向のコミュニケーションを活性化させます。
その過程で、専門性の違いを超えた相互理解が生まれ、結果としてチームの結束力が強まります。
また、失敗を前向きに受け止める文化が育つため、心理的安全性が高まり、メンバーが自由に意見を言いやすくなる効果も期待できます。
こうした風土が根付くことで、持続的に創造性が発揮されるチームが形成されるのです。
顧客体験に基づいた価値あるサービスを生み出せる
従来のビジネスアプローチでは、効率や収益性が優先されるあまり、ユーザー体験が後回しにされることがありました。
しかしデザイン思考では常に「ユーザーがどう感じるか」を軸に考えるため、提供する製品やサービスは自然と顧客体験を重視したものになります。
ユーザーの満足度が向上し、リピーターやファンを生み出すことにつなげ、さらに、体験を中心に据えることで、ブランドへの信頼や共感も強まり、長期的な顧客関係の構築にも繋がってきます。
ユーザーの満足度を上げるため、UI/UXデザインは有力な武器になるはずです。
ProximoではUI/UX専門のコンサルティングを行なっておりますので、ぜひ一度以下のリンクから詳細をご覧ください。
デザイン思考を導入する際の2つの注意点
デザイン思考は非常に有効なアプローチである一方で、「万能ではない」ので注意が必要です。
その効果を最大限に活かすためには、適用する場面や進め方に注意を払う必要があります。
特に、デザイン思考の特性を理解せずに形式的に取り入れてしまうと、期待した成果が得られないどころか、逆にプロジェクトが停滞することもあります。
ゼロベースの発明には向かない点に留意する
デザイン思考は「ユーザーのニーズを深く理解し、それを満たす解決策を導く」ことに長けていますが、まったく新しい技術や理論を生み出すようなゼロベースの発明には不向きです。
これは、プロセスの出発点が常に「既存のユーザー体験」や「現実の課題」であるためです。
つまり、未知の技術を発明することと、既存の課題に寄り添い解決策を創出することは目的が異なるのです。
成果を急ぎすぎるとプロセスの効果が失われる
もう一つの注意点は「スピードを重視しすぎると、デザイン思考本来の効果が薄れる」という点です。
もちろん試作や検証を素早く行うことは重要ですが、それ以上に大切なのは共感や課題定義のプロセスを十分に踏むことです。
現場では「早く成果を出したい」というプレッシャーから、共感や観察を省略してしまうケースがあります。
しかし、その結果として「本質的ではない課題」に時間とリソースを費やしてしまい、結局は解決策が的外れになるリスクが高まります。
上記2点に関して、デザイン思考を取り入れる際、注意しましょう。
デザイン思考と組み合わせやすい手法

デザイン思考を単独で活用することも可能ですが、他のフレームワークや分析手法と組み合わせることで、その効果をさらに高めることができます。
ユーザー理解を深めたり、事業戦略に直結させたりするためには、補助的なツールの活用が欠かせません。以下では、代表的な手法とその活用の仕方を具体的に解説します。
共感マップやジャーニーマップの活用
デザイン思考の第一段階である「共感」を深めるためには、ユーザーの感情や行動を可視化するフレームワークが有効です。その代表例が「共感マップ」と「カスタマージャーニーマップ」です。
共感マップでは「見ていること」「聞いていること」「考えていること」「感じていること」を整理することで、ユーザーの頭の中や心情を構造化できます。
一方、ジャーニーマップはユーザーがサービスや製品に触れる一連の流れを時系列で描き、どの場面で満足や不満が生じているかを把握するために使います。
共感マップやジャーニーマップは課題の「見える化」を通じて、具体的な改善策を導き出す力を持っています。
SWOT分析や事業環境分析との相乗効果
デザイン思考で導き出したアイデアを事業として実現させるには、環境要因や内部資源を踏まえて検討することが不可欠です。ここで役立つのがSWOT分析や事業環境分析です。
SWOT分析では、組織の強み・弱み、外部環境の機会・脅威を整理することで、アイデアの実現可能性やリスクを冷静に判断できます。
事業環境分析を行うことで、外部トレンドや競合の動向を把握し、デザイン思考で得た解決策を市場に適応させる戦略を立てられます。
こうした分析との組み合わせは、アイデアを「実行可能な計画」へと昇華させる重要なプロセスになります。
ビジネスモデルキャンバスによる応用展開
デザイン思考の成果を事業として拡大していくためには、ビジネスモデルの設計が欠かせません。ここで役立つのがビジネスモデルキャンバスです。
このフレームワークでは「顧客セグメント」「提供価値」「チャネル」「収益構造」など9つの要素を一枚のシートにまとめ、事業全体を俯瞰できます。
デザイン思考で生まれたアイデアをキャンバスに落とし込むことで、ビジネスとして成立するかを具体的に検討できるのです。
ビジネスモデルキャンバスは、アイデアを現実の事業へと変換する架け橋となります。デザイン思考と組み合わせることで、創造性と実行力を兼ね備えた成果を生み出すことが可能になるのです。
まとめ
デザイン思考は、単なる問題解決の手法ではなく、ユーザーを中心に据えた価値創出のアプローチです。現代のビジネスにおいては、競争環境が激化し、顧客のニーズも多様化しているため、従来の論理的な枠組みだけでは対応が難しくなっています。
そこで、共感を出発点に課題を定義し、アイデアを形にして検証を繰り返すデザイン思考の考え方が求められているのです。
また、実際のビジネスに応用できる実践性を備えている点が特徴です。多様な意見を取り入れ、プロセスを反復することで、失敗を恐れず改善を重ねられる仕組みが整います。
このアプローチは、新規事業の立ち上げや既存サービスの改善だけでなく、組織文化の変革にも役立ちます。最終的にデザイン思考は、企業と顧客が共に価値をつくり出し、社会に持続可能なインパクトを与えるための重要な手段になるといえるでしょう。
Proximoは、UI/UXデザインで企業が抱える問題解決を支援しています。
例えばKUROFUNE株式会社様では、以下のリンクにあるようにブランディングの支援を行いました。
Proximが行うサービス詳細が気になっていただければ、以下からサービス詳細を知っていただければと思います。