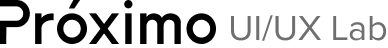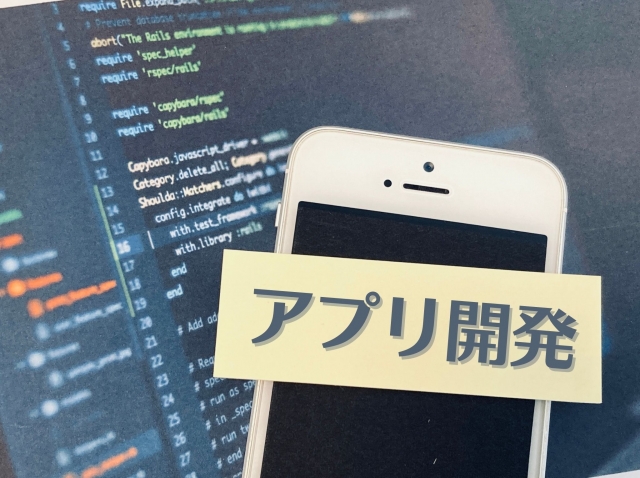システム内製化が企業成長を加速する!知っておきたい導入と活用のすべて

システム内製化は、ビジネス環境が急速に変化する現代において、企業が競争力を維持・強化するために不可欠です。
かつては専門的な領域として外部委託されることが多かったシステム開発ですが、最近では企業自らが開発力を持ち、内製化を推進する動きが加速しています。
今回は、システム内製化の定義からその重要性、メリット・デメリット、導入の成功ポイントまで、幅広く解説します。
目次
システム内製化とは?
外注と内製の違いとは
企業がシステムを導入する際、「外注(アウトソーシング)」と「内製化(インハウス)」という2つのアプローチがあります。
これらは単なる作業手段の違いではなく、企業の開発思想や戦略に直結する重要な選択肢です。
外注は、開発・保守を外部ベンダーに委託することで専門技術や工数を補う形で利用され、比較的短期間で成果物を得られる反面、自社に技術や知見が蓄積されにくいという弱点があります。
一方、内製は社内のリソースでシステム開発を行うため、初期段階ではコストや時間がかかることもありますが、長期的には技術力や柔軟性を社内に蓄積でき、業務との親和性が高いシステムが構築できます。
特に近年は、市場やユーザーのニーズが日々変化しており、それに即応するシステム開発が求められています。そうした背景から、開発体制の柔軟性やスピードが重視されるようになり、内製化の重要性が再評価されているのです。
このように、外注と内製はそれぞれにメリット・デメリットがあるため、企業は自社の目的・状況に応じて適切な選択をする必要があります。
今後は、両者を柔軟に組み合わせる「ハイブリッド型」も注目されるでしょう。
なぜ今「内製化」が求められているのか
急激な市場変化と技術革新が、企業に自社開発力の強化を迫っています。
かつては、ITに関する開発業務を外部に委託することが常識とされていました。
理由は明確で、ITは専門的知識を要する分野であり、技術やノウハウがない企業にとっては、自社で開発するよりもプロに任せた方が安心だったからです。
しかし、時代は大きく変わりました。DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、企業には迅速な対応力と継続的な変化への柔軟性が求められるようになっています。
たとえば、日々変化する市場ニーズや競合の動向に素早く対応するためには、自社の業務内容を深く理解した上で、迅速かつ継続的に改善できるシステムが不可欠です。
外注でそれを実現しようとすると、要件定義やフィードバックのタイムラグが障壁となり、スピード感が損なわれることがあります。
これに対し、内製化であれば、現場と開発の距離が近く、改善点をすぐに反映できる環境が整えやすくなります。
しかし、外注に頼ることのリスクも無視できません。ITベンダーの入れ替えによる情報共有のロスや、ベンダーロックインと呼ばれる過度な依存状態に陥ることで、結果的に開発の自由度や選択肢が狭まることがあるのです。
このような問題を避けるためにも、システム開発における主導権を社内に取り戻す必要があり、それが内製化の重要な理由の一つとなっています。
今後、企業が自律的に成長を遂げるためには、IT部門だけでなく、全社的に「作る力」を高めていくことが必要となるはずです。
その第一歩が、内製化を通じて、自社の業務に適したシステムをスピーディーかつ柔軟に生み出せる体制を構築することなのです。
企業がシステム内製化を進める3つの主要な理由

IT人材不足の克服と技術内製力の向上
日本国内におけるIT人材の不足は、もはや一過性の問題ではありません。経済産業省の報告によれば、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足するという試算も出ています。
このような状況の中で、優秀なエンジニアを外部から採用し続けることは、特に中堅・中小企業にとっては現実的な選択肢とは言えません。採用競争は激化し、報酬水準も高騰しているからです。
こうした背景から、多くの企業が「自社で人材を育成する」という方向へと舵を切り始めています。
内製化は、単なる開発体制の転換にとどまらず、自社に技術力と開発ノウハウを蓄積するための最適な手段です。現場で必要とされる業務システムを自らの手で作り上げていくことで、社員の技術的理解も深まり、システム活用のレベルも向上します。
外部ベンダーでは理解が難しい業務プロセスやカルチャーも、社内人材であれば自然と共有されており、ミスマッチのないシステム開発が実現しやすくなります。
もちろん、社内にIT人材を育てるには一定の時間と投資が必要です。しかし、それを回避するために外注を続けた結果、業務ノウハウやシステム仕様が社内に蓄積されず、同じ課題を繰り返すケースも少なくありません。IT人材不足が深刻化する今こそ、内製化へのシフトが重要な選択となります。
ベンダーロックインからの脱却
システム開発において、外注先のベンダーに長年依存している企業は少なくありません。この状態を「ベンダーロックイン」と呼びますが、実はこれが企業の成長や変革の大きな障害となる場合があります。
また、ベンダーに依存することで、企業は自社の業務フローやシステム全体像に対する理解を持たなくなってしまいがちです。その結果、自社で改善すべき点や新しい仕組みを検討する機会が減り、業務の非効率が放置されてしまうこともあります。
内製化は、こうした依存関係からの脱却を実現するための最も有効な手段となります。
自社で開発・運用できる体制が整えば、ベンダーとの契約内容に縛られることなく、必要に応じた機能改善やシステム連携が可能になります。
もちろん、完全な内製化を一足飛びに目指すのは現実的ではありません。初期段階では外部ベンダーと協業しつつ、段階的に社内に開発スキルと業務理解を移行していくというアプローチが有効だと考えられます。
経営と現場のニーズをつなぐ柔軟な対応力
これまでのシステム開発では、経営層の意向が最優先され、現場の実態や課題が十分に反映されないという問題がしばしば見受けられました。
その結果、せっかく導入したシステムが使いづらい、業務に合っていない、現場で活用されないといった「形だけのIT化」が進んでしまうケースが少なくなかったのです。このような状況を打破する鍵となるのが、内製化による柔軟な対応力です。
内製化によって、システム開発の主体が自社にある状態になると、現場との距離が格段に近くなります。
業務課題をリアルタイムで共有し、実際に使う人の声を聞きながら仕様を決定・改良していくことが可能になります。こうしたプロセスは、ユーザビリティの高いシステムの構築を実現するだけでなく、現場のモチベーション向上や組織内の連携強化にもつながります。
最終的に内製化が実現するのは、現場主導かつ経営視点も取り入れた「現実的なIT戦略」です。ITを活用した変革は、トップダウンだけでも、ボトムアップだけでも成功しません。
そんな内製化に向かう段階の企業では、外部との協業から始まるケースがほとんどです。その外部パートナーをお探しの企業は、是非一度弊社HPをご覧ください。
Proximoでは「UI/UXデザイントレーニング」といった、内製化の支援をしております。
デジタル戦略におけるUI/UX改善にご興味ある方は、以下のリンクからサービス詳細をクリックしてください。
システム内製化の3つのメリット
スピーディーな開発と改善が可能になる
市場環境や顧客ニーズが刻々と変化する現代において、ビジネスのスピードはますます加速しています。これに対応するには、システムの改修・改善を即座に行える体制が必要です。
従来の外注体制では、要件定義から設計、実装、リリースまでに長い時間がかかり、変更要求が出ても即座に対応することが難しいのが現実です。その結果、機会損失が生じたり、ユーザーの不満が蓄積したりするリスクが高まります。
一方、内製化された体制では、社内で開発者が業務部門と直接連携しながらシステム開発を進めることができるため、改善点に気づいたその場で対応できるスピード感が生まれます。
たとえば、販売管理システムにおいて、現場から「あるデータ項目をCSVに出力したい」という要望が出た際、外注の場合は見積・契約・開発・納品といったプロセスを踏む必要がありますが、内製化であれば開発者が要望を直接聞き、その日のうちに実装・リリースすることも可能になります。
このようなスピード感は、顧客満足度の向上、業務効率の改善、そしてビジネスチャンスの最大化に直結します。
社内ノウハウの蓄積と共有が進む
外部ベンダーに開発を委託すると、完成したシステムは手に入るものの、その開発過程や設計思想、構築の背景といった「暗黙知」はベンダー側に蓄積されてしまいます。
これが長期的に見たときの大きな機会損失であり、次回以降の改善やシステム連携時に思わぬ障壁となることもあります。こうした知識を社内に蓄積していくことができる点で、内製化は企業にとって大きなメリットをもたらします。
内製化によって、業務の流れや利用者の声を直接取り込みながら開発が進められるため、「なぜこの機能が必要なのか」「どのような業務課題を解決するための仕様なのか」といった背景情報が、開発者と関係者の間で共有されやすくなります。
組織内に技術的・業務的な知識が蓄積されることで、企業はより「賢く」成長していけるようになります。これこそが、内製化を単なるコストダウン手法ではなく、戦略的な成長施策として捉えるべき理由なのです。
セキュリティレベルの向上と統制強化につながる
情報セキュリティへの関心が高まる中、システム開発における情報管理体制も見直されるようになってきました。
外部ベンダーにシステム開発や運用を委託する場合、どうしてもデータのやり取りや設計情報の外部共有が発生します。その過程で情報漏えいや不正アクセスのリスクが生じるのは避けられません。
内製化は、こうしたリスクを大幅に軽減できる方法の一つです。開発・運用に関するすべてのプロセスを「社内で完結」させることで、外部とのデータ授受を最小限に抑えることができ、情報管理の統制が取りやすくなります。
また、セキュリティポリシーの策定や監査対応も、内製チームが主導で行えるため、全体の統制力が高まります。
社内にノウハウを蓄積しつつ、情報を外部に出さずに守る。これが、これからの時代に求められるシステム開発体制であり、内製化の意義がより大きくなっている理由のひとつです。
システム内製化に伴うデメリットと対策
開発人材確保の難しさ
多くの企業が内製化に挑戦したいと考える一方で、真っ先に直面する課題が「人材不足」です。
特に、一定以上のスキルを持ったエンジニアの採用は年々難しくなっており、競争も激化しています。また、IT業界以外の企業にとっては、エンジニアの確保だけでなく、育成・定着といったマネジメント面でも大きな課題があります。
この問題は、内製化の初期段階において深刻化しやすく、結果的に「人材が集まらないから内製化できない」という悪循環を生むこともあります。
しかし、すべてを正社員のエンジニアで構成しようとするのではなく、業務部門の中にITリテラシーの高い人材を配置したり「業務主導型の開発体制」を構築することが、現実的な打開策となり得ます。
また、外部の支援をうまく活用することも選択肢の一つです。技術顧問や外部パートナーと連携しつつ、段階的に社内の開発力を引き上げていくアプローチは、多くの企業で成果を挙げています。
最終的には、自社の業務とシステムを理解した“内製チーム”を育てていくことが理想ですが、その第一歩として、外部の力を借りることは決して後ろ向きではありません。
今後、内製化を目指す企業にとっては、単なる人材の採用だけでなく、業務部門とIT部門の連携強化、ツール活用、柔軟な体制構築といった複合的な対応が求められるようになります。
品質と保守性の担保の必要性
内製化によってスピーディーな開発が可能になる一方で、その裏には品質や保守性が軽視されるリスクが潜んでいます。
特に、開発経験の浅い人材や業務部門主導で開発が進むケースでは、初期の要件を満たすことに注力するあまり、設計やテストが不十分になることがあります。
その結果、バグの多発や仕様の不整合が生じ、運用フェーズに入ってからのトラブルが増加することになりかねません。
こうした問題に対応するためには、開発プロセスの整備とルールの明確化が不可欠です。
内製化の成否は単に「開発できるかどうか」ではなく、「継続的に価値を提供し続けられるか」にかかっています。スピードと品質の両立を意識した開発体制づくりが、持続可能な内製化には欠かせないのです。
教育コストと時間の問題
内製化を進めるには、開発スキルを持つ人材が社内に必要になりますが、多くの企業ではその人材をゼロから育てる必要があります。
特に、これまでIT部門を外部に依存していた企業では、業務知識とITスキルの両方を兼ね備えた人材の育成が求められます。
また、教育には当然ながらコストが伴います。技術習得には時間がかかり、その間は即戦力として機能しない場合もあります。
初期段階では「教える側」のリソース不足も課題になりますが、過去の開発ノウハウを教材化する、ペアプログラミングを導入する、外部の講師やコンサルタントと連携するなど、さまざまな工夫によって教育効果を高めることが可能です。
教育コストは短期的に見れば負担となりますが、内製化によって開発スピードが上がり、外注費用が削減されるという中長期的なリターンを考えれば、十分に見合った投資といえるでしょう。
成功するシステム内製化の3つの重要ポイント
小規模な導入から始めて段階的に拡大する
システム内製化に取り組む際、多くの企業が最初に誤ってしまうのが、「最初からすべてを内製化しよう」とする方針です。理想を高く掲げることは重要ですが、社内体制が整っていない段階で広範囲に手を出すと、リソースが分散し、品質低下やプロジェクトの停滞を招く危険性があります。
そこで有効なのが、小規模なシステムや業務改善ツールの開発から始め、徐々に内製化の範囲を拡大していくアプローチです。
このような「段階的導入」には、成功体験を得やすく、現場との連携も強化しやすいというメリットがあります。加えて、スモールスタートであれば、学習コストや初期投資も抑えられ、経営層からの理解と支援も得やすくなる傾向にあります。
社内外のリソースを活用してチーム体制を構築
内製化を成功させるには、開発スキル、業務知識、マネジメント力など、多岐にわたる能力が求められます。しかし、すべてを自社内だけでまかなうのは非現実的です。だからこそ、社外の専門家やパートナー企業の力を上手に取り入れ、段階的に内製体制を強化していくことが求められます。
たとえば、初期フェーズでは外部ベンダーに設計や実装の一部を委託しながら、自社の担当者がそのプロセスに密接に関与することで、技術の習得や業務知識の共有が自然に進みます。
すべてを自前で完結しようとするのではなく、「外部の知見を取り込みながら、自社に合った内製力を育てていく」ことが、持続可能な内製化体制の構築において最も実践的なアプローチです。
ノーコード/ローコードツールの活用で内製化を加速
これまでシステム開発といえば、専門的なプログラミングスキルを持ったエンジニアの仕事でした。
しかし、ノーコードやローコードといった技術の進化により、非エンジニアでもシステム開発に参加できる時代が到来しています。これらのツールを活用することで、業務部門主導の内製化が現実のものとなりつつあります。
ノーコードツールは、プログラミングなしで画面設計や業務フロー構築が可能であり、特に定型業務や簡易的な業務改善に非常に適しています。
ローコードツールは、多少のプログラミング知識を必要としますが、その分柔軟性が高く、既存システムとの連携や高度な処理にも対応できます。これらのツールを使えば、スピーディにプロトタイプを作成し、現場でテストしながら改善していくというアジャイルなアプローチが可能になります。
このように、ノーコード/ローコードツールは、企業のIT部門だけでなく、現場の業務担当者を開発の主役に変える可能性を秘めています。誰もが開発に参加できる環境を整えることで、内製化は「特別なプロジェクト」ではなく、日常業務の一部として自然に浸透していくのです。
ノーコード/ローコードツールの選び方と導入の流れ

自社の開発目的と業務内容に合致しているかを確認
ノーコード/ローコードツールは便利な技術ですが、万能ではありません。市場には数多くのツールが存在し、それぞれに得意・不得意があります。そのため、導入に際しては「自社の開発目的」と「対象となる業務内容」を明確にし、それに最も合致するツールを選ぶことが最も重要です。
選定の際には、導入したい機能を一覧化し、それぞれの業務プロセスと照らし合わせながら、対応可否や使い勝手を評価していくことが大切です。
ノーコード/ローコードの選定は、単に「開発しやすさ」だけでなく、導入後の運用定着まで見据えた視点で行い、最初に「何を、誰が、なぜ作るのか」を徹底的に言語化することが、成功の第一歩となります。
ランニングコストと導入費用のバランスを検討
ツール導入の際、多くの企業が初期費用に目を向けがちですが、重要なのはむしろ「継続的に運用していくための費用」です。
ノーコード/ローコードツールはサブスクリプション型で提供されることが多く、利用ユーザー数やストレージ容量、機能制限などによって月額費用が大きく変動します。
導入前には、必要な機能の利用条件や制限内容を詳細に確認し、想定される最大規模での費用シミュレーションを行っておくことが望ましいです。
コスト面では、価格だけでなく「価値とのバランス」も重視すべきです。多少費用がかかっても、業務効率や開発スピードが向上するのであれば、それは十分に見合った投資となります。
サポート体制や学習リソースの有無も重要な選定基準
どんなに高機能なノーコード/ローコードツールでも、実際に使う現場の担当者が操作方法や仕組みを理解していなければ意味がありません。
そのため、ツール選定時には機能や価格だけでなく、「サポート体制」や「学習リソースの充実度」も重視すべき重要なポイントです。
ツール導入は「使い続けられるかどうか」が成否を分ける要素です。だからこそ、技術だけでなく教育・支援の充実度という視点からも、しっかりと比較・検討を行うことが求められます。
内製化に適した業務領域と適さない領域の見極め方
内製化を推進する際、多くの企業が「すべてを内製しよう」と意気込んでしまいます。しかし、これは現実的でも効果的でもありません。リソースが限られている中で、最大限の成果を出すには、内製化に適した領域とそうでない領域を戦略的に選別することが不可欠です。
まず、内製化に向いているのは、自社の業務に密着しており、頻繁な仕様変更や改善が求められる業務です。
たとえば、営業報告ツール、日次の業務フロー改善、部門間の情報連携を目的とした簡易アプリケーションなどです。
一方で、内製化に不向きな領域もあります。セキュリティ要件が非常に高いシステム、複雑な外部システムとの連携を必要とする基幹業務、大規模データ分析基盤、リアルタイム処理が求められるインフラ系の開発などは、高度な専門性が要求されます。
本当に内製化すべき業務はどこなのか、外注と併用すべき業務はどこなのか。
これを明確に線引きしたうえで、内製と外注のバランスを取りながら、段階的に拡大していく視点が必要です
この内容をお読みいただき、「内製化に向いていない領域」だとお感じの方は、一度弊社までお問い合わせください。
デジタル戦略におけるUI/UX支援のプロが、貴社で内製化すべきなのか、それとも外注すべきなのか、お伝えいたします。
内製化を実現するための社内体制づくり
システム内製化を成功させるには、優秀なエンジニアを採用することや、ツールを導入することだけでは不十分です。
最も重要なのは、内製開発が継続的に機能する「体制づくり」にあります。これは、組織の中で誰がどの役割を担い、どのように連携してプロジェクトを進めていくかという設計図のようなもので、これを曖昧にしたまま進めると、成果が出ずに頓挫するリスクが高くなります。
まず必要なのは、内製化を推進するための専任チームの設置です。
推進責任者(プロダクトオーナー的役割)を明確にし、その下に業務理解のある担当者や、システム要件を設計できる人材、実際の開発・保守を担うエンジニアなど、必要な役割を定義します。
ここでは、単にIT部門だけでなく、業務部門からの人材も積極的に参加させることが重要です。
また、社内教育の体制も整える必要があります。新しいツールや開発手法を導入する場合、チーム内で共通の知識基盤を持っておくことは不可欠です。
内製化を「技術導入の話」にとどめず、「組織戦略」として捉えることが、真に強い開発力を持った企業への第一歩となります。
まとめ
これまで外注中心だったシステム開発の体制が、今、大きく見直されています。
自社で開発・改善を行う「内製化」は、業務に密着した柔軟な開発を可能にし、スピード・品質・コストのバランスを自社の判断でコントロールできる強力な手段となります。
しかし、その実現には、適切な体制づくり、ツールの活用、人材の確保と育成、そして経営層から現場までの意識改革が必要不可欠です。
この記事で紹介したように、内製化には数多くのメリットがある一方で、導入や定着には計画性と段階的なアプローチが求められます。
目的を見失わず、部分的な成果を全体へと拡張しながら、時間をかけて内製文化を育てていく姿勢が、最終的に企業全体の競争力を底上げします。
とはいえ、内製化に向かない部分は外部と一緒に進めることが、最もスピード感を落とさず推進できる部分です。
Proximoでは、内製化研修の事例は豊富にございます。
・株式会社ケイライン ビジネス システムズ(川崎汽船グループ)事例
具体的には、企業向けに以下のような研修内容を提供しています。
・基礎研修
UI/UXデザインの基本的な考え方やプロセスを学ぶための座学を実施。デザイン原則やユーザビリティ向上に役立つ知識を提供します。
・実践演習
実際のプロジェクトを題材にした演習を通じて、学んだ知識を実践に活かせるスキルを養います。UI/UXデザインをプロジェクトに適用する方法を学びます。
そのほか、企業のニーズに合わせてカスタマイズしたUI/UXトレーニングを提供しており、企業内でのデザインスキルの内製化もサポート可能です。
従業員教育の仕組みづくりや内製化にご興味のある方は、以下から詳細をご覧ください。