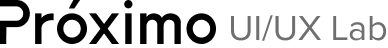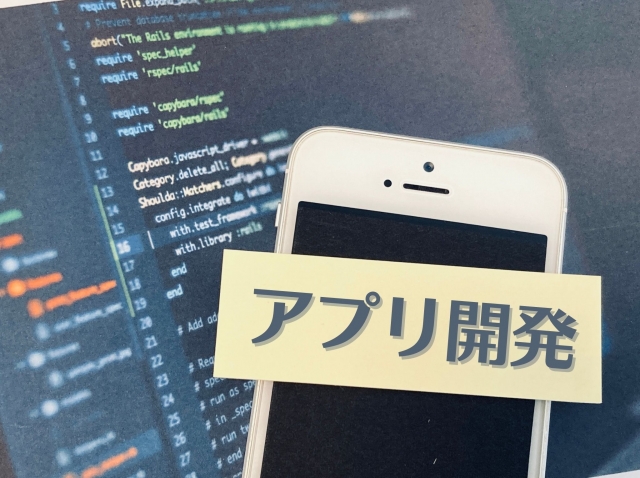アジャイル開発とスクラム開発の違いを徹底解説!実践できるために理解しよう

アジャイル開発とスクラム開発には、違いがあることは理解しながらも、「アジャイルとスクラムって結局何が違うの?」という疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
今回は、アジャイル開発とスクラム開発の違いを丁寧に解説しながら、それぞれの特徴、メリット、適用シーン、現場での実践方法までを詳しく解説します。
目次
アジャイル開発とスクラム開発の違いは?
アジャイル開発とスクラム開発という2つの言葉は、ソフトウェア開発やプロジェクトマネジメントの現場で頻繁に登場します。
しかし、それぞれの意味や立ち位置を正しく理解できていないまま使われるケースも少なくありません。
両者の違いを正確に把握することは、プロジェクトの選定・推進において大きな意味を持ちます。
アジャイル開発は、一言でいえば「価値観」や「考え方」を表す包括的な概念です。
変化への柔軟な対応、顧客との継続的な連携、反復的な開発を重視するスタンスが基本にあります。これは単なる技術的な方法論ではなく、チームの行動や意思決定の指針にまで及ぶものです。
必要に応じて計画を見直し、最も価値のある機能から優先的に提供していくという考え方が、この開発スタイルの本質です。
一方のスクラム開発は、アジャイル開発の理念を実践するためのフレームワークの一つです。
つまり、スクラムはアジャイルの一部分であり、アジャイルの価値観を現場で具体的に実装するための方法論だと理解するのが適切です。
スクラムには明確なルールとイベント(スプリント、デイリースクラム、レビューなど)が存在し、アジャイルの原則に沿って進行することを前提としています。そのため、「アジャイルでやっています」という現場の多くが、実際には「スクラムでやっています」ということも少なくありません。
では、なぜこの違いをしっかりと理解しておく必要があるのでしょうか?
その答えは、プロジェクトやチームに最適な手法を選ぶためです。アジャイルという考え方自体には複数の実践手法が含まれており、スクラムはその中でも比較的広く用いられているに過ぎません。
つまり、アジャイルという上位概念を理解したうえで、その中の一手法としてスクラムを選択する、という視点が重要になるのです。
アジャイル開発の本質について
アジャイル開発の流れと短期間サイクルの特徴
アジャイル開発では、「早く動くものを届けて、すぐにフィードバックをもらう」というサイクルを何度も繰り返すのが基本です。一般的にこのサイクルは「イテレーション(反復)」と呼ばれ、1〜4週間の短期間で開発、テスト、レビューを行います。
この流れの中では、最初に大まかな方向性と優先度を決めてから、最も重要な機能や価値の高い部分から着手します。
完成した機能はすぐにユーザーに見せ、改善点や新たなニーズを吸収して、次のイテレーションに活かします。これにより、開発が終わるころには「最初に考えたもの」ではなく「本当に必要とされるもの」が完成している状態を目指せるわけです。
アジャイル開発のこの短期間サイクルは、仕様変更や優先順位の入れ替えにも柔軟に対応できる仕組みであり、関係者とのコミュニケーションが密になることで、開発スピードと顧客満足度の両立が可能になります。
アジャイル開発とウォーターフォール開発の考え方の違い
アジャイルとウォーターフォールの最も大きな違いは、「変化をどう捉えるか」にあります。ウォーターフォール型では、プロジェクトの初期段階で要件をすべて定義し、それに基づいて設計・実装・テストと進めていきます。つまり、「計画通りに進めること」が成功の鍵になります。
一方、アジャイル開発では「計画はあくまで仮説」として扱い、実際の進行中に得られる学びや顧客の声をもとに、仕様や方針を柔軟に変えていきます。このアプローチは特に、先が読めないプロジェクトや、ユーザーのニーズが流動的な状況で大きな威力を発揮します。
この考え方の違いは、開発プロセスだけでなく、プロジェクトの進め方や組織文化にまで影響を与える要素となっています。
スクラム開発とはどんなアプローチか?

スクラム開発の中心となるプロダクトバックログとスプリント
スクラム開発では、「何を作るか」を管理するのがプロダクトバックログ、「いつまでに作るか」を管理するのがスプリントです。この2つはスクラムの中核ともいえる存在です。
プロダクトバックログは、顧客やユーザーの要望、技術的改善点など、開発対象のあらゆる要素をリスト化したもので、プロダクトオーナーが常に優先順位を更新しながら管理します。これにより、常に「今、一番価値の高いこと」に集中できるようになります。
スプリントは、1〜4週間の開発期間を指し、その期間内でどのバックログ項目に取り組むかをチームで決定します。短期間で結果を出すことで、早期にユーザーからのフィードバックを得ることができ、次のスプリントにすぐ活かせるのが特徴です。この反復の仕組みにより、プロダクトは段階的に進化していきます。
スクラムチームにおける役割分担とチーム主体の文化
スクラムでは、「プロダクトオーナー」「スクラムマスター」「開発チーム」の3つのロールが明確に定義されています。それぞれが独立した責任を持ちながらも、緊密に連携することで、自律的で強いチームが形成されます。
プロダクトオーナーは、顧客の声を代弁し、製品の方向性を決定する役割です。スクラムマスターは、チームがスクラムの原則に則って動けるよう、障害の除去や改善のサポートを行います。
そして開発チームは、実際の実装を担当しながら、日々の意思決定をチーム内で行います。
特徴的なのは、スクラムにおいては「上司」や「指示者」が存在しないことです。あくまでチームが主体的に動き、必要に応じて外部と連携を取るという自律的な運営が前提となるのが特徴です。
スクラム開発のプロセスと各イベントの具体的な進行方法
スクラム開発の成功には、スクラムが定義する一連のイベントを正しく理解し、実践することが不可欠です。
スクラムの開発サイクルは「スプリント」という一定期間の単位で区切られます。
スプリントの始まりには「スプリントプランニング」が実施され、プロダクトオーナーと開発チームが協力して、今回のスプリントで何を達成するかを決定します。
この場では、プロダクトバックログから優先度の高い項目を選び、それを「スプリントバックログ」としてまとめ、具体的な作業計画を立てていきます。
スプリントの実行期間中は、毎日「デイリースクラム」が開催されます。このミーティングでは、チームメンバーが現在の進捗、直面している課題、次にやることについて簡潔に共有します。
このイベントの目的は、情報の透明性を保ち、ボトルネックを早期に発見することにあります。
また、スプリントの終盤には「スプリントレビュー」が行われ、チームはステークホルダーに対して今回のスプリントで何を達成したのかをデモなどを通じて説明します。
そしてスプリントの最後に実施されるのが「スプリントレトロスペクティブ」です。このイベントでは、チームメンバーがスプリント全体を振り返り、何がうまくいったか、どこに課題があったかを率直に話し合います。
具体的なアクションプランを設定し、次回に繋げることがスクラムの継続的な成長に繋がるわけです。
アジャイル開発とスクラム開発の関係性とそれぞれの適用シーン
アジャイル開発とスクラム開発は、非常に密接な関係性を持ちながらも、それぞれ異なる役割と適用シーンを担っています。
この違いを明確に理解しないまま導入してしまうと、チームの混乱やプロジェクトの失敗を招きかねません。
特に実務においては、「アジャイルだからスクラムを使わなければいけない」といった誤解が生まれがちですが、実際にはアジャイルには複数の手法が存在し、状況に応じた選択が求められます。
両者の関係性を踏まえると、それぞれの適用シーンも異なってきます。
たとえば、プロジェクトの要件が変わりやすく、顧客との密なコミュニケーションが求められる場合には、アジャイルの導入が効果的です。
しかしその中でも、チームが小規模で自律的に動ける環境、かつプロダクトに対して継続的にフィードバックが得られるような現場であれば、スクラムが非常に適しています。
一方で、スクラムはすべての組織やチームに最適というわけではありません。
たとえば、複数チームで大規模に開発を行う必要があるプロジェクトでは、スクラム単体では対応しきれないことがあります。そのような場合には、Scaled Agile Framework(SAFe)やLeSS(Large-Scale Scrum)といったスケーリング手法を併用します。
皆様に押さえておいてもらいたいのは、アジャイル開発とスクラム開発は、目的と手段の関係にあることで、アジャイルは変化に強く、顧客に価値を届けることを重視する「開発の姿勢」であり、スクラムはそれを現場で実現するための「実践的フレームワーク」です。
アジャイル・スクラム開発におけるUI/UXデザインの重要性とその連携方法
なぜUI/UXがアジャイル・スクラムにおいて不可欠なのか?
アジャイルやスクラムの目的は、できるだけ早く、できるだけ価値の高いプロダクトを顧客に届けることにあります。その価値とは、機能だけで測られるものではなく、「使いやすさ」「心地よさ」「継続して使いたくなる体験」といったUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)によって大きく左右されます。
どれほど素早くリリースされたプロダクトであっても、ユーザーにとって直感的でなく、操作が煩雑であれば、すぐに離脱されてしまいます。逆に、最小限の機能でも、わかりやすく、気持ちよく操作できるプロダクトであれば、ユーザーの評価は高まり、次のフィードバックや改善にも良い影響を与えます。
UI/UXデザインとスクラムチームの連携のコツ
スクラム開発では、短いスプリント単位でプロダクトを進化させていくため、UI/UXデザイナーとの連携が欠かせません。理想的なのは、UI/UXデザイナーをスクラムチームの一員として組み込むことです。これにより、開発と並行してプロトタイピングやユーザビリティ検証を行い、機能と体験の両面からプロダクトの品質を高めることができます。
開発者とデザイナーの間で壁を作らず、相互に理解し合う文化を作ることが、アジャイルにおけるUI/UX連携の鍵です。
UI/UX改善を前提としたプロダクト開発の進め方
アジャイル開発では、UI/UXも“完成して終わり”ではなく、継続的に改善されるべき要素です。ユーザーからのフィードバックや、分析ツールを用いたデータ収集を通じて、どの操作が使いづらいのか、どこで離脱しているのかを把握し、改善のサイクルを回していくことが必要です。
この観点では、「UI/UXに関するバックログ項目」をきちんと管理し、優先順位をつけてスプリントに組み込むことが重要です。体験の質は、単なるビジュアルではなく、ビジネス価値の一部として扱うべきです。
UI/UXデザインが与えるビジネスインパクト
UI/UXの良し悪しがビジネスに与える影響は、決して軽視できません。例えば、ECサイトにおいて購入ボタンの配置や、入力フォームのシンプルさだけで、コンバージョン率が大きく変わることはよくあります。
スクラムの反復開発は、こうした体験価値の改善と非常に相性が良く、UI/UXをビジネス戦略に組み込むことで、プロダクトの価値と企業の成長を加速させることができます。
アジャイル開発に向いているプロジェクトの特徴とは?
アジャイル開発は万能ではありません。だからこそ、その適性を見極めることが重要です。
アジャイルの強みを最大限に活かすためには、どういった条件が揃っているプロジェクトに向いているのかを正しく理解する必要があります。
適切な環境でアジャイルを採用すれば、短期間で大きな成果を生むことが可能になるでしょう。
アジャイル開発が真価を発揮するのは、「要求が流動的」であり、「開発初期の段階」で「全ての仕様が明確に定まっていない」プロジェクトです。
たとえば、新規プロダクトの立ち上げや、実証実験(PoC)フェーズの開発などは典型的な例です。
また、アジャイル開発は顧客やビジネス部門との「継続的な対話」が求められるため、ステークホルダーとのコミュニケーションが密に取れる体制があるかどうかも重要なポイントです。
顧客がフィードバックを積極的に返してくれる、あるいはプロダクトオーナーがビジネス視点を持って意思決定できる場合、アジャイルのサイクルは非常にスムーズに回ります。逆に、顧客が受け身だったり、意思決定のスピードが遅かったりすると、アジャイルの柔軟性は活かされにくくなります。
スクラム開発に最適なチーム構成とスキルセット

スクラム開発を成功に導くためには、プロセスやツールよりも「人」が最も重要です。
どれほどスクラムのルールを理解していても、それを実行するチームが適切な構成とスキルを備えていなければ、期待される成果を得ることは難しくなります。スクラムが重視するのは“自己組織化されたチーム”であり、その実現には役割の明確さと相互の信頼、そして多様なスキルが不可欠です。
スクラムチームは基本的に「プロダクトオーナー」「スクラムマスター」「開発チーム」という3つの役割で構成されます。
それぞれが単なる肩書きではなく、明確な責任を持ち、相互に補完し合うことでスクラムのフレームワークが機能します。
まずプロダクトオーナーは、開発すべき機能や優先順位を決定する役割であり、顧客の声を最も近くで受け取り、プロダクトバックログを管理します。
次にスクラムマスターは、チームがスクラムの原則を守り、スムーズに機能するよう支援する存在です。いわば“ファシリテーター”のような役割であり、チームの障害を取り除き、プロセス改善を促進します。
そして開発チームは、実際にプロダクトを作るエンジニアたちで構成されますが、スクラムでは「フロントエンド」「バックエンド」「テスター」などの専門職に分かれて動くのではなく、横断的に協力する“クロスファンクショナルチーム”が理想とされます。
つまり、メンバーが特定の役割に固執せず、状況に応じて柔軟に役割を補完し合える構造で、この柔軟性が、スクラムの強みである変化への対応力を支える土台となります。
まとめ
アジャイル開発とスクラム開発は、混同されがちな言葉ですが、実際には異なるレイヤーに位置する概念です。
この違いを理解しないまま導入を進めてしまうと、「アジャイルをやっているつもりが、単に形だけのスクラムイベントを回している状態」になってしまうことがありますので、今回の記事を参考にしてもらえると幸いです。
UI/UXデザイン支援を行うProximoでは、アジャイル開発の柔軟性により、UI/UXを継続的に改善することが大事だと考えています。
それはUI/Uを軽視した開発を行うと、ユーザーの期待を超えられず、失敗するケースが多いからです。
たとえばProximoでは、以下のようなUI/UX支援の実績がございます。
ユーザーの変化が激しい中、UI/UXの継続的な改善は必要不可欠です。
以下のリンクから弊社サービス詳細を知ってください。